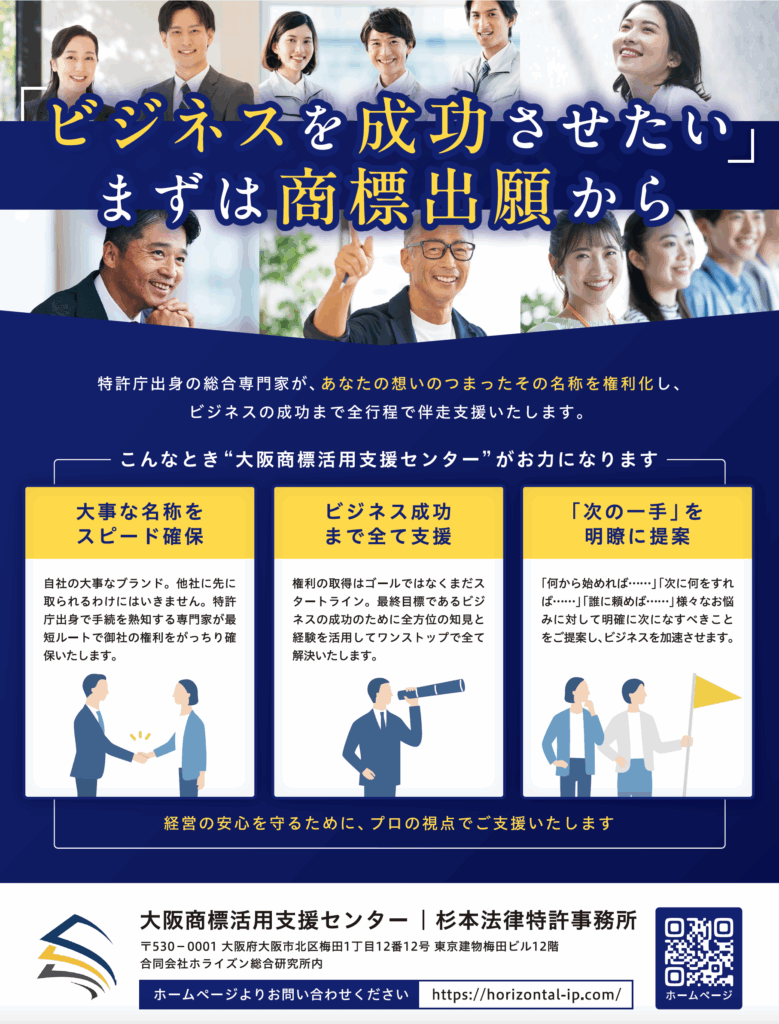相談者(60代男性)
相談者(60代男性)
定年退職後、おにぎり屋の自営を始めました。娘が「おにぎりくん」「おにぎりちゃん」という可愛い商品名を考えてくれたので、商標登録を考えたのですが、弁理士会の無料電話相談で聞いてみたところ、このようなほぼ商品そのものに名称は商標登録できないと説明されました。せっかくの娘の提案なので何とか権利化できればと思うのですが良い方法はないでしょうか
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
おにぎりだと、その名称である「おにぎり」や原材料のお米や海苔、さらにはその産地や効能などの表示そのままでは商標登録は難しいです。オリジナルの名称で商標出願するのが一般的ですが、もしそのおにぎり店を将来的に娘さんに次いでもらうことまで考えるのであれば、まずはロゴマークとして商標登録し、社会でそのマークが認知されるよう営業活動を続けていくことが考えられます。
普通名称は商標登録できない
商標制度における最も重要な原則の一つは、社会で広く使われている「普通名称」は商標登録できないという点です。例えば、おにぎりを商品として販売する際に「おにぎりくん」や「おにぎりちゃん」といった名前を登録しようとしても、原則として登録は認められません。なぜなら「おにぎり」という言葉は日本社会で日常的に使われており、誰かが独占してよいものではないからです。商標の役割はあくまで「出所表示」、つまり消費者が「どの会社の商品か」を判別できるようにする点にあります。社会の共通財産ともいえる普通名称を特定企業が独占してしまえば、消費者や競合他社にとって大きな不利益を生じ、公平性を害することになってしまいます。
そのため、商標登録を検討する際には、他と区別できるオリジナルで識別力のある名称を考案することが原則です。ユニークな名称は独自性を持ち、消費者に強い印象を残すと同時に、模倣されにくい利点があります。もっとも、事業者の立場からすると「どうしても普通名称を利用したい」という場合も多いのが現実です。なぜなら、普通名称は直感的にわかりやすく、商品やサービスの内容をすぐに連想させるからです。マーケティング上の即効性は高い一方で、商標制度上の制約があることが問題です。
そこで本稿では、このように普通名称に近い言葉をどう扱えばよいか、どのような工夫をすればブランド戦略に役立てられるかを段階的に解説していきます。
社会でどのように使われているかを観察しよう
商標登録を検討する場合、まず大切なのは「その言葉が社会でどのように使われているのか」を丁寧に観察することです。たとえば食品や飲料業界では、商品名に産地や原材料を強調するケースがよく見られます。「北海道産○○」「無添加△△」「ビタミン豊富□□」といった表現は、確かに商品の魅力を伝えるには有効ですが、商標としては説明的に過ぎ、識別力が認められない可能性が高いのです。商標は「誰の商品か」を明示するための制度なので、商品の品質や効能を表す普通の表現を一企業が独占することはできません。
そこで重要になるのが、社会でどのような言葉が既に使われ、どのような言葉がまだオリジナル性を持っているかを調べることです。市場調査やインターネット検索を通じて、同業他社がどのようなネーミングを行っているかを把握すれば、登録の可能性がある言葉とそうでない言葉の区別がついてきます。特に注意が必要なのは、有名商品の名前をもじって使う場合です。消費者にとってわかりやすいかもしれませんが、これは不正競争防止法上の問題を引き起こす可能性があり、法的リスクを伴います。他社の信用に便乗する行為は市場の混乱を生み出し、結果的に訴訟リスクを背負うことにもなりかねません。
したがって、商標登録を本気で考えるなら、極力オリジナルな名称を創作するのが最も望ましい道です。社会での使われ方を観察することは、単なる参考にとどまらず、ブランド戦略全体の出発点です。観察を通じて得られる知見が、その後の商標戦略やネーミングの方向性を左右します。つまり「観察」は、商標登録に挑む前の基礎体力づくりともいえます。
ロゴで登録する
普通名称をそのまま文字で商標登録するのは難しいですが、工夫次第で実現可能性が広がります。その一つが「ロゴとして商標登録する」方法です。例えば「おにぎり」という言葉は単独では登録されませんが、独自のフォント、特徴的な図形、カラーリングを組み合わせてロゴ化すれば、商標として認められる可能性が高まります。ロゴは単なる文字ではなく、視覚的デザインとして独自性を持つため、商標制度上も識別力があると評価されやすいです。
ただし、この場合に得られるのはあくまで「ロゴ全体に対する権利」であり、文字そのものを独占する権利ではありません。他社が異なるデザインで同じ言葉を用いることを止めることはできない点には注意が必要です。しかし、ロゴが消費者の目に焼き付けば、それ自体が「誰の商品か」を示す力を持つようになります。実際、消費者は単なる言葉よりも、特徴的なロゴやデザインを記憶に残しやすいものです。
また、ロゴとして登録するメリットは法的側面にとどまりません。マーケティング戦略の観点からも、ロゴはブランドイメージを形成する強力なツールになります。消費者は商品を選ぶ際に視覚的な印象に大きく左右されるため、独自性のあるロゴは競争上の優位性を築く助けとなります。つまり、普通名称を使いたい場合には、まずロゴ化して商標登録を試み、そこから社会的な認知を得ることが現実的なスタートラインです。
ロゴとしての定着からオリジナル化へ
ロゴとして市場に浸透させることができれば、次に起こるのは言葉そのものの「オリジナル化」です。人は商品を認識するとき、視覚的要素に加え、言葉の響きや連想からも強く影響を受けます。たとえ普通名称であっても、ロゴとともに繰り返し目にすることで「その言葉=あの会社の商品」という連想が形成されていきます。例えば「おにぎりくん」という言葉が、特定の会社のロゴと強く結びついた場合、消費者は自然と「おにぎりくんといえばあの会社」を想起するようになります。
商標法上も「使用による識別力の獲得」という仕組みが存在します。本来は普通名称に過ぎなかった言葉でも、長年の使用実績や広告宣伝の効果によって、消費者に特定の出所を示す力が備わった場合、商標登録が認められる可能性があるのです。このプロセスは一朝一夕に達成されるものではなく、継続的な努力と社会的浸透が不可欠です。しかし、一度定着すれば、普通名称が強力なブランド資産へと変貌します。
つまり、普通名称をブランドにしたい場合は、まずロゴとして定着させ、そこから言葉の認知を積み重ねていくことが効果的です。ロゴが社会的に浸透すれば、言葉そのものが自然にオリジナルのブランド名として消費者に認識されるようになります。結果として、もともと登録が難しかった普通名称を、最終的に商標として確保できる可能性が生まれます。
どうしても普通名称をおさえたければ
それでもなお「どうしても普通名称を独占的に確保したい」という強いニーズがある場合、より戦略的かつ長期的なアプローチが必要になります。その一つが、まず普通名称を直接関連のない分野で商標登録するという方法です。商標制度では商品やサービスの区分が細かく分けられており、直接関連しないジャンルであれば普通名称でも登録できる可能性があります。そこでまずは異なる分野で登録し、商標使用の実績を積むことが考えられます。
次に、その商標を使う対象を少しずつ本来の普通名称が示す分野に近づけていきます。例えば、飲食店の屋号として普通名称を登録し、一定の実績を築いた後、その名前を食品の販売に展開していくといった手法が考えられます。このように段階を踏んで消費者に浸透させることで、普通名称であっても「特定の企業のブランド」として定着し、最終的に商標登録が可能になる場合があります。
ただし、この戦略は時間もコストもかかり、短期的な成果を期待することはできません。広告宣伝や販売活動を通じてブランドの信用を積み重ねる必要があり、その過程では一貫したブランドメッセージを発信し続けなければなりません。それでも、成功すれば普通名称を強力なブランド資産として独占できるという大きなリターンがあります。要するに「普通名称をどうしてもおさえたい」のであれば、長期的な計画と忍耐強い努力が必須です。
まとめ
普通名称は、その性質上、原則として商標登録できません。社会で誰もが使う言葉を特定の企業が独占してしまうと、公平性や消費者の利便性が損なわれるためです。そのため、商標登録を考える際には、できる限りオリジナルで識別力のある名称を採用することが望ましいのです。しかし、現実的には普通名称を利用したい場面も多く、その場合には段階を踏んだ工夫が求められます。
最初のステップは、社会でどのように言葉が使われているかを丁寧に観察することです。その上で、まずはロゴとして商標登録し、社会に浸透させることが現実的な方法となります。ロゴが消費者に認知されれば、その中の言葉も自然に浸透し、やがて自社オリジナルのブランドとして受け止められるようになります。さらに、異分野での登録や長期的な使用実績を積むことで、普通名称そのものを商標として確保できる可能性も開かれます。
結論として、普通名称を商標として活用するには「一足飛びではなく、段階を踏んでブランド価値を育てていく」戦略が欠かせません。焦らずに時間と労力をかけて育て上げることで、普通名称が唯一無二のブランド資産へと昇華し、競争上の大きな力となります。
当センターでは難しい商標登録についても様々な観点で考察して、最終的なビジネスの成功につなげるための道筋を徹底的に探し出します。下記よりお気軽にご相談ください。