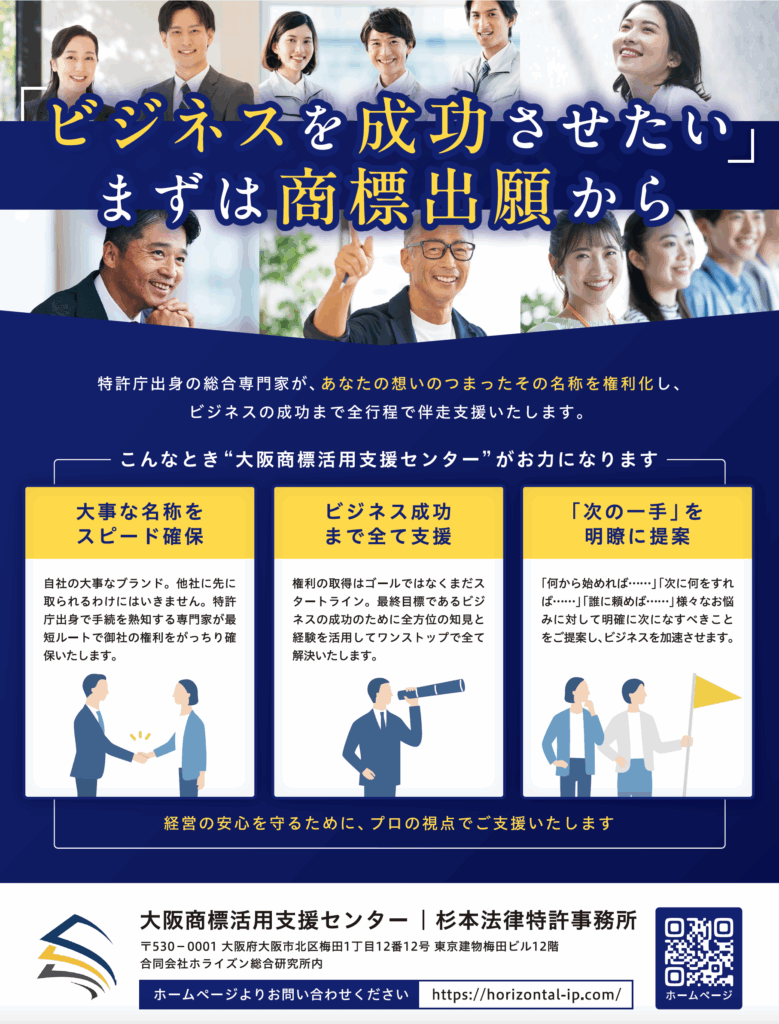相談者(30代男性)
相談者(30代男性)
特許庁から先行類似商標があるという拒絶理由通知を受けました。内容を確認しましたが、確かに全体としてみると似ているようにも見えるため、類似していないと反論するのでは勝算はあまり高くないようにも思います。かといって、先行商標と被らないよう商標権の範囲を絞るのでは私のやりたいビジネスが展開できません。他により良い方法はないでしょうか。
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
その先行商標の権利者が直近3年間商標を使用していなければ特許庁に不使用取消審判を起こすことができます。「使用していない」という事実を確認するのは難しいですが、ネット検索で商標の名称が出てこなければ先行商標を取り消すことができるかもしれません。ただし、審判を起こしても相手方が使用の事実を立証すれば取消できませんし、審判を起こすにはそれなりに費用も必要であるため、多くの方はまずは非類似の主張を主として考え、不使用取消請求は予備的な手段として位置付けています。
先行商標との類否を争うのが難しそうな場合
商標を出願した際、審査官から「先行登録されている商標と類似するため拒絶」という理由で拒絶理由通知を受けることは珍しくありません。特に日本の商標審査においては、商標の文字や読み、観念が部分的に一致しているだけでも「類似」と判断される場合が多いため、申請者側からすると納得感が得にくいこともしばしばです。
このような場面で取り得る対応としては大きく三つ考えられます。一つは、審査段階で先行商標と自分の商標は非類似であると主張することです。具体的には、取引の実情や需要者の認識を踏まえて「誤認混同は生じない」と説明する戦略です。これは王道のアプローチであり、審査官を説得できれば最も負担が少なく登録を勝ち取ることができます。
二つ目は、自らの権利範囲を縮小する方法です。具体的には、指定商品や役務の範囲を限定し、先行商標のカバーする範囲と被らないように調整することです。この場合、商標そのものは守れますが、ビジネスの自由度が減ってしまうというデメリットがあります。
三つ目の方法が、不使用取消審判を申し立てることです。先行して登録されているものの実際には使用されていない商標について、法律上は3年間使われていなければ取り消しを求めることができます。つまり、自分の商標が本来は登録可能であるにもかかわらず「使われてもいない商標」に邪魔されている場合、その障害を取り除く手段として活用できます。
もっとも、実務の現場ではまず「非類似」であると主張するのが第一の選択肢になることが多いです。しかし、あまりにも先行商標と似ており、論理的に勝ち目が薄いと考えられるケースでは、この不使用取消審判を検討する価値が出てきます。そこで本稿では、そうした場合に不使用取消審判を仕掛ける条件や勝算について掘り下げていきます。
不使用取消審判とは?
不使用取消審判とは、商標法第50条に基づく制度で、登録された商標が「継続して3年以上日本国内で使用されていない」場合に、誰でもその取り消しを請求できる手続です。目的は、実際に使われていない商標が市場において独占的な障害物として残り続けることを防ぐ点にあります。
申立人が行う手続自体は比較的シンプルです。特許庁に対して、対象となる商標が過去3年間使用されていないことを理由に取消を求める書面を提出します。ここで特徴的なのは、申立人が「使用されていないこと」を直接証明する必要はなく、立証責任は商標権者側にあるという点です。
審判を受けた商標権者は、直近3年以内に当該商標を指定商品・役務について実際に使用していることを証明しなければなりません。その際には客観的で信頼性のある証拠が求められます。単なるデジカメ写真や社内作成の書面は容易に作成可能で証明力が低いため、特許庁は重視しません。代わりに、取引先との請求書や納品書、広告の掲載誌、販売データなどが必要となり、立証のハードルは意外に高いです。
したがって、不使用取消審判は一見すると申立人に有利な制度に見えますが、相手方が十分な使用実績を証拠で提出すれば取り消しはできません。逆に言えば、商標権者が証拠を用意できなければ、実際に使用していたとしても取り消しとなる可能性がある点が大きな特徴です。
このように、不使用取消審判は「使われていない商標を整理するための制度」であると同時に、「証拠を出せない権利者から商標を取り除く制度」として機能しています。
不使用取消審判をする前になすべきこと
不使用取消審判は、いきなり申し立てれば勝てるというものではありません。相手方が実際に商標を使用しているかどうかを見極めるため、事前の調査が欠かせません。まず最初に行うべきは、相手方企業の公式ウェブサイトを確認することです。商品紹介ページやプレスリリース、オンラインショップなどを見て、該当の商標が実際に使用されている形跡があるかを調べます。
次に行うべきは、インターネット上での流通実態の調査です。検索エンジンやECサイトで商標の文字列を入力し、過去数年分の商品情報を確認します。特にAmazonや楽天、Yahoo!ショッピングなど大手プラットフォームを検索すれば、商標が使われている商品が市場に流通しているかどうかの手掛かりを得られます。
また、相手方以外の事業者がその商標を使用している場合も要注意です。第三者の利用実績がある場合、単なる模倣ではなくライセンス契約に基づいて使われている可能性があります。もし契約に基づく正規使用であれば、商標法上は「商標権者による使用」と同視されるため、不使用取消の対象にはなりません。そのため、契約関係の有無も重要な調査項目です。
さらに、対象商標が海外で使用されている場合も考慮する必要があります。海外での使用実績があっても、日本国内に輸入実績がなければ「日本国内での使用」とは認められません。しかし、輸入商社などを通じて少量でも国内販売されていれば、使用実績として扱われる可能性が高いです。そのため、貿易実務の調査や輸入履歴の確認が有効です。
このように、申し立ての前にはネット検索や市場調査を徹底的に行い、商標が実際に使われていないことを可能な限り確認しておくことが大切です。
事前調査には限界がある
事前調査を入念に行ったとしても、その結果に過信してはいけません。ネット検索や市場調査によって把握できるのは、あくまで公開されている情報に限られるからです。例えば、インターネット上で販売の痕跡がまったく見当たらなくても、特定地域に限定して商品が流通していたり、特定の得意先への直販という形で継続的に使われている可能性があります。こうした取引は広告やECサイトに現れないため、外部からはなかなか把握できません。
また、商標権者が証拠を提出できるかどうかは、市場での知名度や取引規模と必ずしも比例しません。ごく少量の販売実績であっても、それを裏付ける客観的な請求書や納品書があれば「使用」と認められます。つまり、市場で目立たないからといって「不使用」と断定するのは危険です。逆に、調査で確認できる程度の広告や販売の痕跡が見つかったとしても、それが3年以内の使用実績であるかどうかを特定するのは難しく、証拠能力の点で使えないケースもあり得ます。
さらに、商標権者が大企業である場合には、証拠収集の体制が整っているため、表面的に使用実績が見えにくくても、内部資料を揃えて審判に提出することが可能です。こうした場合、申立人側が「使われていないに違いない」と思って申し立てても、予想外に強力な証拠が提示されて敗訴することが少なくありません。
逆に、中小企業や個人が商標権者である場合は、証拠の保管や管理が十分でないことも多いため、実際には使用していたとしても証拠不十分で取り消されてしまうこともあります。このように、不使用取消審判は「実際に使っていたかどうか」以上に「証拠を提出できるかどうか」が勝敗を左右する制度だといえます。
したがって、申立を決断する際には「勝つ確率がどの程度あるのか」を冷静に見積もる必要があります。相手の業態や企業規模、商品展開の仕方などを分析し、証拠が揃えにくいタイプの相手かどうかを推測することが一つの判断材料となります。負けるリスクをゼロにはできませんが、そのリスクを見込んだうえで挑戦するかどうかを決めることが重要です。
費用負担の問題
不使用取消審判を利用するうえで避けて通れないのが費用と時間の負担です。申立に必要な印紙代は数万円に過ぎませんが、実務上は弁理士に依頼するのが一般的であり、その報酬は案件の複雑さによって数十万円程度に及ぶことがあります。さらに、相手方が反論してきた場合には意見書への対応や追加資料の準備が必要になり、その分の費用がかさみます。
審判は東京の特許庁で行われるため、地方の企業が自ら対応するのは現実的ではありません。代理人への依頼はほぼ必須となり、そのぶん中小企業や個人事業主にとっては大きな負担となります。審理が長引けばその間に事業計画が停滞するリスクもあります。
一方、大企業にとってはこれらの費用や時間は事業戦略上のコストとして十分に許容可能です。むしろブランド戦略にとって重要なネーミングを確保できるのであれば、数十万円規模の投資であっても合理的と考えられます。この違いは、制度の実効性に大きな差を生み出しています。
さらに、負担は金銭面だけではありません。自社ブランドの将来性を見据えて不使用取消審判を選ぶか、それとも商品範囲を縮小してでも登録を優先するかといった経営判断が求められるのです。特にスタートアップ企業にとっては、短期的な資金繰りとの兼ね合いもあり、単純に「やれば勝てるかどうか」だけでは判断できない難しさがあります。
このように、不使用取消審判は制度としては公平に開かれていますが、実際には資金力や経営資源の豊富さによって利用可能性が大きく異なります。企業規模による格差を助長する制度であることを理解したうえで、自社にとって本当に合理的な選択かどうかを見極めることが重要です。
まとめ
先行商標との類否を争うのが難しい場合、不使用取消審判は大きな可能性を秘めた選択肢となります。しかし、その実態を丁寧に見ていくと、この制度にはメリットとデメリットが明確に共存しています。
まず、制度の根本的な趣旨は「使われていない商標を整理して市場の健全性を保つこと」にあります。これは新たに市場に参入する事業者にとって公平な競争環境を確保するものであり、社会的にも意義があります。しかし一方で、勝敗は相手が証拠を提出できるかどうかに左右され、実際の市場での使用状況と必ずしも一致しないという不安定さを抱えています。
また、事前調査をどれだけ入念に行っても、証拠の有無までは見極められません。市場で痕跡がなくても裏で使われている可能性は常に残りますし、逆に市場で多少の実績が見えても証拠不十分で取り消される場合もあります。この不確実性こそが、不使用取消審判の最も大きなリスク要因といえるでしょう。
さらに、費用負担の問題も軽視できません。大企業にとっては合理的な投資であっても、中小企業にとっては資金面での大きな障害となります。つまり、この制度を実際に使えるかどうかは企業規模や経営体力によって大きく異なり、制度そのものの利用可能性に格差が生じやすいです。
したがって、不使用取消審判を検討する際には、勝算を冷静に分析することと同時に、費用対効果を慎重に見極める必要があります。勝てば大きな成果を得られる一方で、負ければ費用と時間の損失だけが残るため、リスクマネジメントが欠かせません。
最終的に、この制度は「絶対に勝てる勝負」ではなく「挑戦する価値があるかどうかを経営判断する勝負」だといえます。自社のブランド戦略に照らし合わせ、資金力、事業計画、リスク許容度を総合的に勘案し、最適な道を選ぶことが肝要です。
当センター長は特許庁審判部で数多くの不使用取消審判に触れた経験があり、この分野は特に得意としております。下記よりお気軽にご相談ください。