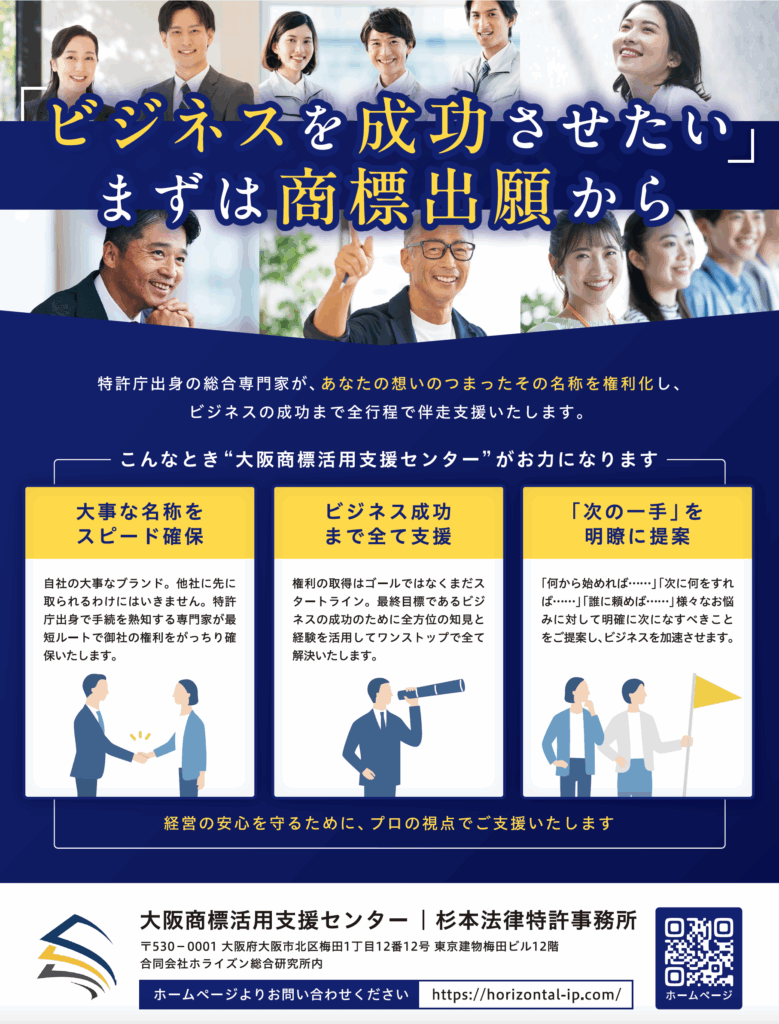相談者(40代男性)
相談者(40代男性)
良いマークを思いついたので自分で商標出願して権利を取得することができました。せっかく取得した権利ですし、維持コストもかかるので何らかの事業化ができればと考えていますが、何から手をつけていけばよいかわかりません。このような場合、皆さんどのような手順を踏んで事業化を進めていくのでしょうか。事業化といっても新たに会社を設立して、というようなことまでは現時点では考えていません。
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
商標は自らの商品やサービスに活用するのが原則です。しかし、自ら使用する予定がない場合は他社に貸し出してライセンス料収入を得ることが基本的な活用法です。ライセンス先に心当たりがあれば、権利の長所を売り込んで商談を進めていくべきです。見込み客がまだ定まっていない場合はまずはこれを整理してみることが大事です。ライセンス契約は非常に奥が深いので、知的財産に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
基本は自らの商品・サービスに使用する
商標を取得した場合、まず基本となるのは自社の商品やサービスに使用することです。商標の最大の役割は、消費者がそのマークや文字を見たときに「これはあの会社の商品だ」と認識できるようにする点にあります。つまり、商標は企業と顧客を結び付ける「顔」として機能し、信頼や品質保証のシンボルとなるのです。そのため、せっかく権利を取得しても、自社で十分に活用しなければ本来の力を発揮できません。
商標を活用するにあたって重要なのは、自社のビジネスの整理です。事業計画を見直し、どの分野で商品やサービスを展開するのか、その対象顧客は誰なのか、どの地域で展開するのかを明確にしておく必要があります。これが曖昧なまま商標を出願すると、実際の事業と出願範囲がかみ合わず、商標が有効に機能しないリスクがあります。例えば、飲食事業を展開する予定で「食品」関連の商標を取得したにもかかわらず、後に雑貨や衣料品へと事業を広げた際に、商標の範囲が足りず再度の出願を迫られるケースがしばしばあります。
また、商標の出願内容は出願後に追加や変更を行うことができません。これは特許や意匠と同様、権利の安定性を守るためのルールです。したがって、最初の出願時点で将来的な事業展開を含め、慎重に考え抜いた内容にすることが極めて重要です。この段階での判断ミスは後から修正できないため、長期的に事業を考慮した戦略的な出願が求められます。
さらに、商標には文字、図形、ロゴマーク、立体的な形状、さらには音など多様な種類があります。どの種類を選択するかによって事業への適合度が変わってきますので、自社のビジネスの特性や顧客の接点を踏まえて検討する必要があります。ロゴマークで視覚的に印象づけるのか、あるいは商品名そのものを商標とするのかによって、顧客への訴求の仕方は変わってきます。
当センターでは、この最初の出願設計段階を丁寧に支援しています。なぜなら、この部分こそが事業化の出発点であり、ここでの判断が商標の将来価値を大きく左右するからです。商標を自らの商品やサービスに付して顧客に浸透させることが、事業化の第一歩であることを忘れてはなりません。
自社で使用しない場合貸し出す
商標を取得したにもかかわらず、自社で直接使用しないケースも存在します。例えば、独自に考案した優れた図柄やネーミングを持っていても、自社の事業計画とは合致せず活用できない場合です。そのようなときに有効な手段が、商標を他社に貸し出してライセンス料収入を得る方法です。商標は適切に活用すれば不動産のように継続的な利益を生み出す可能性を秘めています。
特に「良いアイデアだからとりあえず商標を取っておこう」と考えて出願した人には、このケースが多く見られます。例えば、インパクトのあるブランド名を思いついたものの、自社では活用の場がない。しかし、そのブランド名を使いたいと考える企業は存在するかもしれません。このような場合、ライセンス契約を通じて権利を貸し出すことにより、安定的な収益源となる可能性があります。
不動産は老朽化すれば価値が下がりますが、商標の強みはむしろ時間の経過とともに認知度が高まり、ブランド価値が上昇することすらあります。そのため、適切なライセンス先が見つかれば、長期にわたり半永久的な収益を生み続けることができます。
ただし、ライセンス料の設定や契約内容は非常に繊細で、単純ではありません。商標の知名度、使用する商品の価格帯、使用地域の広さ、使用期間など、多くの要素を勘案して決定する必要があります。場合によっては、相手方の営業戦略や販売見込みに応じてライセンス料の形態を固定額ではなくロイヤリティ方式にすることもあります。こうした交渉には複雑な駆け引きが伴うため、専門家に相談して進めるのが安全です。
また、ライセンスを与える相手が信頼できるかどうかも極めて重要です。不適切な相手に商標を使用させると、ブランドイメージの毀損につながるリスクがあります。商標は単なる収益源ではなく、企業や個人の信用と直結する資産です。したがって、貸し出す場合には経済的な側面だけでなく、相手先の事業内容や企業倫理まで十分に調査して判断することが求められます。
ライセンス先が見当たらない場合の対応策
商標を取得したものの、自社では使用せず、さらに適切なライセンス先がすぐに見つからない場合も少なくありません。その際には、まず自社の商標をどのような層が利用してくれる可能性があるのかを明確に描き出すことが必要です。つまり、潜在的な利用者像を設定することが出発点となります。
例えば、商標がかわいらしいキャラクターであれば、子ども向けの商品や教育関連の企業が利用者候補となるかもしれません。逆に、シンプルで洗練されたロゴであれば、ファッションやデザイン関係の企業が関心を持つ可能性があります。このように、商標の特徴を踏まえて「どのような業種や市場が適合しそうか」を考えることが第一歩です。
次に、描き出した利用者像をもとに、具体的な見込み客をリストアップしていきます。ターゲットを漠然と考えるだけでは前進しないため、会社名や担当部署レベルまで絞り込んだリストを作成することが実務上は欠かせません。このリスト作成は時間と労力を要しますが、精度が高いほど後の営業活動が効率的に進みます。
リストアップができたら、実際に営業活動を行います。自社に営業ノウハウやリソースが不足している場合は、専門の営業代行業者に依頼することも多くあります。特に商標ライセンスのような特殊な取引は、一般的な営業活動とは異なる知識や経験が求められるため、外部に委託する方が合理的な場合も少なくありません。営業代行会社はネットワークを持ち、効率的に見込み客にアプローチできるという利点があります。
営業活動を通じて商談が成立すれば、契約締結へと進みます。このとき注意すべきなのは、契約書の内容です。ライセンス契約は単なる売買契約とは異なり、使用範囲や期間、品質管理の方法、違反時の対応など、多岐にわたる事項を取り決める必要があります。これを怠ると、後にトラブルに発展する可能性が高まります。したがって、契約書は必ず知的財産の専門家にチェックしてもらうべきです。
ライセンス先が見当たらない状況は、一見すると袋小路のように思えるかもしれません。しかし、見込み客の層を丁寧に描き出し、具体的なリストに落とし込み、粘り強く営業活動を続けることで突破口が開けることは少なくありません。商標は有形の商品と違って劣化するものではないため、焦らず戦略的に取り組む姿勢が求められます。
権利の管理
商標を中長期的に事業化していくためには、権利の適切な管理が欠かせません。商標を取得しただけで満足してしまう人もいますが、権利は「持っているだけ」ではなく「どのように維持・運用するか」が価値を左右します。特にライセンス契約を結ぶ場合には、契約書で重要事項を明確に取り決めることが第一歩となります。
契約においては、使用できる範囲や地域、対象商品、期間、ロイヤリティの算定方法などを細かく定める必要があります。これを曖昧にすると、相手が契約範囲を超えて使用したり、収益配分でトラブルになったりする恐れがあります。商標はブランド価値そのものであるため、契約上の不備が企業の信用に直結する可能性があります。
また、契約締結で終わりではなく、その後の使用状況をモニタリングすることが重要です。例えば、契約相手が商標を正しく使用しているか、ブランドイメージを損なうような使い方をしていないかを定期的に確認することが求められます。特に品質管理条項を設け、一定の基準を守ることを契約で義務付けておくと安心です。商標の価値は品質と密接に結びついており、低品質な商品に使われるとブランド価値が一気に下がってしまう危険があります。
さらに、商標は登録から10年ごとに更新手続が必要です。期限を過ぎてしまえば権利が消滅してしまい、せっかく築き上げたブランドを失うことになりかねません。更新漏れは意外と多く、管理体制が甘い企業では重大な損失を招くことがあります。そのため、期限管理を徹底し、使用している商標は確実に延長手続きを行うことが肝要です。
一方で、使っていない商標をいつまでも維持し続けるのが得策とは限りません。権利を維持するためには費用がかかるため、不要になった商標は見切りをつけることも合理的な選択です。使用状況を定期的に点検し、必要な権利は確実に維持し、不要なものは整理していくことで、商標ポートフォリオ全体の効率的な運用が可能になります。
商標の管理は、単なる形式的な手続きにとどまらず、ブランド価値を守り、将来の収益を確保するための重要な取り組みです。怠れば築き上げた資産が一瞬で失われるリスクがある一方、適切に管理すれば事業に長期的な安定をもたらすことができます。
事前準備が重要
商標を事業化する上で忘れてはならないのが、事前準備の重要性です。商標は取得した時点で価値が生まれるわけではなく、それをどのように活用するかによって初めて意味を持ちます。そして、活用の効果を最大化するには、出願前から慎重に準備を進めておくことが欠かせません。
まず、自社で使用する場合には、出願内容と展開するビジネスの内容に齟齬がないことを確認する必要があります。事業計画と商標出願がずれてしまうと、商標が使い勝手の悪いものになり、結果的に事業化の足かせとなります。例えば、国内市場を想定して商標を取得したものの、数年後に海外展開を進める段階になって国際的な保護を受けられず、新たな出願コストや時間的ロスが生じることがあります。このような事態を避けるには、事業の方向性を十分に検討した上で商標戦略を組み込む必要があります。
また、ライセンスを予定している場合でも、相手先が未定であれば、その探索に時間を要します。商標を取得してから慌てて相手を探すのでは遅く、出願段階から「どのような企業が関心を持ちそうか」という視点を持つことが大切です。相手を探し始めるタイミングが早ければ早いほど、適切なパートナーと出会える可能性は高まります。
ライセンス契約においても、契約締結後に発生し得るリスクを先読みして備えることが求められます。例えば、相手が契約違反をした場合の対応、知名度が上がりすぎて第三者による模倣が増えるリスク、経済環境の変化によるライセンス料の妥当性など、多くのシナリオを考慮する必要があります。これを一企業だけでカバーするのは難しいため、知的財産の専門家に早期に相談しておくことが極めて有効です。専門家の知見を取り入れることで、後のリスクを大幅に軽減できます。
さらに、商標は「誰がどのように使用するのか」を明確にすることが大切です。この視点を早い段階で持つことで、出願内容に反映でき、将来的な活用の幅が広がります。使用主体や使用方法を曖昧にしたまま出願すると、後に柔軟性を欠いてしまう恐れがあります。事前に使用イメージを固めることが、商標を真に事業化するための基盤となります。
このように、事前準備は単なる形式ではなく、商標の価値を最大化するための必須プロセスです。早めに準備を整え、リスクや可能性を洗い出すことで、商標は単なる権利から実際の収益源へと成長していきます。
まとめ
商標を事業化するためには、単に取得するだけでは不十分です。まずは自社の商品やサービスに使用して顧客との関係を築くことが基本となります。そのうえで、自社で使用しない場合にはライセンスを通じて収益化を図る方法もあり、適切な相手を見つける努力が欠かせません。ライセンス先がすぐに見つからない場合でも、ターゲットを明確にし、営業活動を継続することで可能性を広げることができます。
また、商標は取得後の管理が極めて重要です。契約内容の明確化、使用状況の監視、更新手続の徹底、不要な権利の整理などを適切に行うことで、長期的なブランド価値を維持することができます。そして、そのすべての基盤となるのが事前準備です。出願前から自社の事業戦略を見据え、使用者や使用方法を明確にし、専門家の助言を得ながら計画を立てることで、商標は真に事業化へとつながっていきます。
商標は目に見えない資産ですが、その価値は企業の成長や信用に直結します。丁寧に設計し、活用し、管理し続けることで、商標は単なる登録記号ではなく、事業を支える柱として機能します。
当センターではこうした権利の事業化に関する手続全般をサポートさせていただきます。下記よりお気軽にご相談ください。