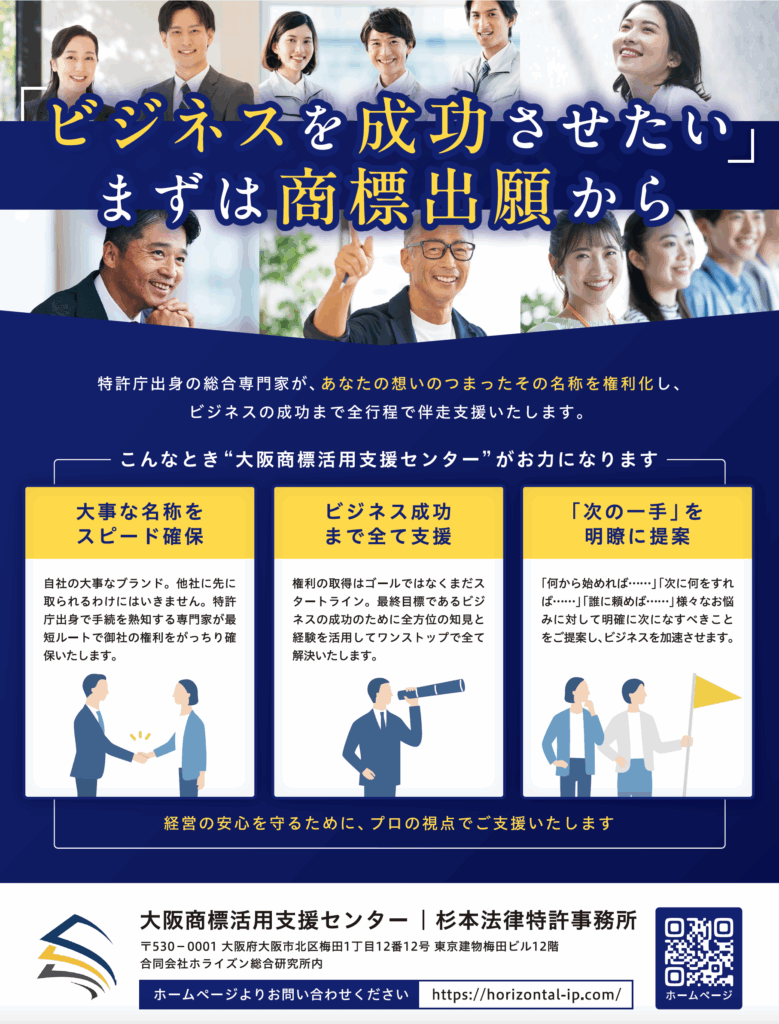相談者(40代男性)
相談者(40代男性)
ようやく商標権を取得できました。私は会社員であるため、私自身がこの権利を使って商売をすることはありませんが、魅力的な名称ですので、他社に貸し出そうと考えています。愛着のある名称なので大切に使ってほしいのですが、できれば対価も高く設定できると嬉しいです。相手がどのような商売に権利を活用するのかわからないため、対価を決めるのも難しそうなのですが、皆さんはどのような方法でライセンス料を設定しているのか教えてください。
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
ライセンス料の設定には、契約時の一時金として受領するか契約期間にわたってもらうものであるか、契約期間にわたってもらうものであっても、固定額か相手の収入などに応じて変動する価格に設定するか、といった観点で場合分けしながら細かく設定するケースが一般的です。おっしゃる通り、相手のビジネスの内容によって受け取る金額や方法が変わってきますので、まずは相手のビジネスの内容とそのリスクをしっかりと理解したうえで、税金の観点での損得も考慮しながら少しでも有利な内容を試行錯誤していくことが多いです。
商標のライセンス料は相手のビジネスを見て決める
商標のライセンス料を決める際に最も重要なのは、相手方がその商標をどのようなビジネスに活用し、どの程度の利益を生む可能性があるかを冷静に分析することです。単純に「有名な商標だから高く」とか「小規模だから安く」といった安直な考えではなく、商標が相手の事業計画においてどれほどの価値を生むかを客観的に見極める必要があります。
たとえば、地域限定で小規模に展開する飲食店チェーンと、全国展開を目指す大手メーカーでは、同じ商標を使用しても経済効果が全く異なります。さらに、その事業がどの程度のリスクを伴うかも重要です。リスクが高い新規ビジネスに対しては、ある程度低めのライセンス料でハードルを下げる場合もありますし、逆に安定した大企業との契約では長期的に利益を確保できるように高めに設定することもあります。このように、相手のビジネス規模・収益性・成長可能性、さらには事業リスクを総合的に勘案してライセンス料を決めることが、商標権者にとってもライセンシーにとっても納得のいく取引につながります。
一時金(イニシャル・ペイメント)を設定するケース
商標ライセンス契約において、一時金(イニシャル・ペイメント)を設定することは珍しくありません。この一時金は、契約締結時にライセンシー(商標を使う側)がライセンサー(商標権者)に対して支払うもので、商標を使用できる権利を獲得する「入場料」のような位置付けです。
一時金を設定する理由としては、商標を使用する側がビジネスを開始する段階で、一定のコミットメントを示すことにあります。ライセンサー側にとっては、事業の成功が不透明な段階でも、最低限の対価を確保できるというメリットがあります。一時金の金額設定は、商標の知名度や信頼性、ライセンシーの事業規模、初期投資額などを総合的に考慮して決めます。
また、一時金は返還不要であるため、ライセンシーにとってはリスクも伴います。したがって、ライセンシー側は一時金の負担が重くなりすぎないように、出来高払方式(ランニング・ロイヤリティ)とのバランスを調整することが一般的です。契約条件としては、一時金を分割払いにしたり、初年度のロイヤリティと相殺するなどの工夫も可能です。お互いの立場を尊重しながら、公平な額を設定することが重要です。
固定額払方式(ランプサム・ペイメント)を設定するケース
固定額払方式(ランプサム・ペイメント)は、商標ライセンス契約において比較的わかりやすい支払方法です。この方式では、商標を使用する対価として、使用期間や使用地域に関係なく、一定額をまとめて支払う仕組みです。たとえば、毎月5万円といった形で、契約時に総額を定めてしまいます。
固定額払方式のメリットは、ライセンサー側にとっては将来の出来高に左右されずに安定した収入を確保できる点にあります。一方でライセンシー側にとっても、売上が思ったより伸びた場合でも追加で支払う必要がないため、利益を最大化できる可能性があります。しかし、ビジネスが思うように伸びなかった場合は固定額の負担が重く感じられるリスクもあります。
金額設定は、商標の市場価値、ライセンシーの想定売上、使用期間などを基に交渉で決められます。また、支払い方法については、全額を一括で支払うケースもあれば、分割払いとするケースもあります。固定額払方式は、ライセンシー目線では事業の予測が比較的容易で、安定した収益が見込めるビジネスに向いており、ライセンサー目線では事業リスクのあるビジネスに向いています。ここで、金額を過小評価するとライセンサーにとって損失につながるため、慎重な収益予測が欠かせません。
出来高払方式(ランニング・ロイヤリティ)を設定するケース
出来高払方式、いわゆるランニング・ロイヤリティは、商標ライセンス契約の中でも最も多く使われる形態の一つです。この方式では、ライセンシーの売上高や製造数量に応じてライセンス料が発生します。たとえば、売上の3%をライセンス料として支払うといった具合です。
出来高払方式の大きな特徴は、ライセンサーとライセンシーがビジネスの成果を分かち合う点にあります。ライセンシー側にとっては、ビジネスが軌道に乗るまでの資金負担を抑えやすく、初期のリスクを軽減できるメリットがあります。一方、ライセンサー側も商標の知名度や信頼性が相手の売上に直結する場合、将来的に大きな利益を得られる可能性があります。
ただし、出来高払方式には売上計上の透明性が重要です。不正確な売上報告を防ぐために、定期的な監査権を契約に盛り込んだり、報告書提出義務を課すなどの取り決めが欠かせません。料率をどの程度にするかは、業界の慣例や商標の影響力、ライセンシーの利益率などを参考に交渉して決めます。特に海外との取引では料率の相場感が異なることもあるため、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
最低保証額(ミニマム・ロイヤリティ)を設定するケース
商標ライセンス契約では、出来高払方式を採用する場合でも「最低保証額(ミニマム・ロイヤリティ)」を設けることが多いです。これは、売上が予想より伸びなかったとしても、ライセンサーが最低限の収入を確保できるようにするための制度です。
最低保証額を設定しないと、ライセンシーが十分な販売活動を行わずに権利を寝かせてしまった場合、ライセンサー側には何の利益も発生しません。これを防ぐために、例えば年間100万円以上のロイヤリティを保証するという形で合意し、売上高に応じた料率で計算した金額がそれを下回った場合は差額を補填して支払う仕組みとします。
ライセンシー側にとっては一定のリスクになりますが、ブランドを活用する以上、ある程度の責任を果たす意味でも妥当です。ただし、保証額が高すぎると小規模な事業者にとっては負担が重くなりすぎ、契約自体がまとまらない可能性もあります。そのため、両者で事業計画を具体的にすり合わせ、現実的な最低保証額を設定することが重要です。万が一、事業計画を大幅に下回る場合の見直し条項を入れるなど、柔軟な運用方法も検討しましょう。
これらを組み合わせて最適な方式にカスタマイズする
実際の商標ライセンス契約では、一時金・固定額払方式・出来高払方式・最低保証額のいずれか一つを単独で採用するだけでなく、複数の方式を組み合わせて最適な条件を作ることが一般的です。なぜなら、商標の価値は使用形態や事業規模、展開地域、業界特性によって大きく異なるため、画一的な方式では双方にとって不公平が生じるおそれがあるからです。
たとえば、契約締結時にイニシャル・ペイメントとして一時金を受け取りつつ、事業の売上に応じて出来高払方式のロイヤリティを設定する方法があります。この場合、ライセンサーは初期段階で一定額を回収でき、長期的に売上が伸びればさらにロイヤリティ収入を増やせます。また、最低保証額を付け加えて、ライセンシーが商標を適切に活用しない事態を防ぐことも大切です。
大手企業との大規模なプロジェクトであれば、固定額と出来高払いを段階的に適用するハイブリッド型も考えられます。契約内容を固める際は、専門家と相談しながら「どの条件をどう組み合わせれば双方の利益を最大化できるか」をじっくり検討しましょう。標準的な形にとらわれず、個別の事情に合わせてオーダーメイドで設計することが、商標ライセンス契約成功のカギとなります。
その他に取り決めるべき事項
商標ライセンス契約では、ライセンス料の方式や金額だけでなく、支払いに関する詳細な条件を取り決めておくことが不可欠です。まず重要なのが、ライセンス料の計算方法です。出来高払方式の場合、売上金額の範囲をどこまで含めるのか(税抜か税込か、返品分の扱いはどうするか)などを明確にしておかないと、後々トラブルの原因になります。
また、計算期間についても注意が必要です。多くの場合、月次または四半期ごとに売上を集計し、ロイヤリティを計算します。報告の頻度と方法、必要な証拠資料の提出方法、ライセンサーによる監査権限を条項に盛り込むと、透明性を確保しやすくなります。
さらに、支払時期と支払方法も取り決めておきましょう。振込先や通貨、為替レートの基準、遅延があった場合の遅延損害金の取り扱いなども契約書に明記しておくと安心です。特に海外の取引先との間では、税金や源泉徴収のルールも関係してくるため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをお勧めします。
これらの細かい点を曖昧にしたまま契約してしまうと、後で紛争に発展しやすいので、必ず具体的かつ明確に取り決めることが、良好なライセンス関係を維持するポイントです。
事業の内容だけでなくリスクにも配慮が必要
商標ライセンス料の設定では、相手の事業計画や市場規模だけでなく、そのビジネスが抱えるリスクの度合いにも十分配慮することが大切です。たとえば、新規参入のビジネスでまだ売上の見込みが立たない場合、出来高払方式をメインにしつつ、一時金を抑えめに設定して、相手の初期負担を軽減する工夫が有効です。一方で、すでに一定の顧客基盤がある事業であれば、最低保証額を高めに設定し、ブランドの無駄使いを防ぐべきです。
また、相手の経営体制や財務状況、取扱商品・サービスのリスクも重要です。例えば、法令規制が厳しい業界や事故リスクが高い商品を扱う場合は、ライセンサーとしては損害賠償などの法的リスクも視野に入れ、ライセンス料の内訳や契約条項でリスクヘッジを講じる必要があります。
逆に、相手が中小企業やスタートアップであれば、過剰なライセンス料は相手の経営を圧迫し、結果的にビジネスが継続できずに自社の収益にもマイナスです。こうしたケースでは段階的にライセンス料を引き上げる条項を入れるなど、柔軟な対応が求められます。
このように、単に「どれだけ儲かりそうか」だけでなく、事業リスクを総合的に評価し、最適なライセンス条件を設計することがトラブルを防ぎ、長期的な信頼関係を築くカギとなります。
税金のことも合わせて考えておこう
商標ライセンス料を受け取る側は、税金の取り扱いについてもきちんと理解しておく必要があります。たとえば、会社員が個人として商標ライセンス料を受領する場合、それは「雑所得」として課税されるケースが一般的です。雑所得は他の給与所得などと合算して総合課税されるため、所得税の税率も累進課税の影響を受けます。
また、商標ライセンスが事業規模とみなされると事業所得となる可能性があるため、税務署に適切に必要な申請などを行い、控除できる経費を計上すべきです。
さらに、海外企業にライセンスする場合には、源泉徴収税が発生する国もあります。日本と相手国の租税条約によって税率が軽減されるケースもありますが、これを適用するには税務署への届出や証明書の提出が必要です。支払いを受ける際の口座や通貨も含め、税務上の手続きを怠ると余計な税負担が生じる可能性があるので、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
「せっかくのライセンス料が税金で思ったより残らなかった」ということのないように、契約締結前から税務面も含めて計画を立てておくことが大切です。
まとめ
商標ライセンス料の決め方は一見複雑に思えますが、ポイントを整理して考えればそれほど難しくはありません。まず大切なのは、相手のビジネス規模や収益性、そしてリスクを客観的に見極めることです。その上で、一時金、固定額払方式、出来高払方式、最低保証額などの仕組みを組み合わせ、自社にとっても相手にとっても納得のいく形を探ることが必要です。
また、ライセンス料の金額だけでなく、計算方法、支払方法、報告義務、監査権限といった細かい条件もきちんと契約書に盛り込み、後のトラブルを防ぐようにしましょう。そして、商標ビジネスは税金の問題も無視できません。個人で受領する場合と法人で受領する場合とでは税務上の取り扱いが異なりますし、海外との取引では源泉徴収や租税条約も考慮する必要があります。
このように、商標ライセンス契約は単なるお金の取り決めではなく、双方のビジネスを発展させるための信頼関係の土台でもあります。専門家の助言を受けつつ、自社に有利で無理のない条件を整えて、納得感のある契約を結びましょう。
当センターでは弁理士だけでなく弁護士・公認会計士・CFPとしても活躍する専門家が貴方の大切な権利のライセンスについてより良いライセンス契約の成立を目指します。下記よりお気軽にご相談ください。