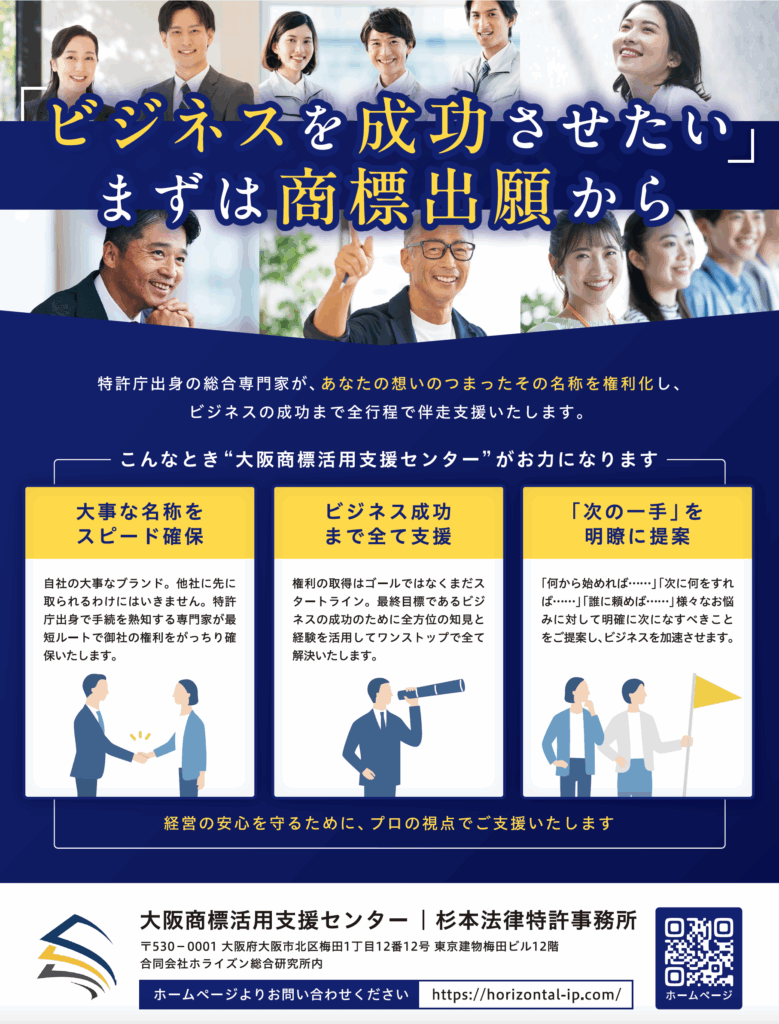相談者(30代男性)
相談者(30代男性)
所定のフォームに必要事項を入力すれば打合せをせずに商標出願してくれるシステムを見かけました。特許事務所に行く手間も省けますし、それで安くなるのであれば非常に便利な制度だと思うのですが、多くの方は依然、弁理士に依頼して商標出願しています。自動出願システムを利用するうえで何かデメリットなどがあるのであれば教えてください。
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
商標の自動出願システムは特許事務所がAIを活用して商標出願プロセスの自動化できる部分を自動化したもので、最後は弁理士が目を通しているため大きな危険性はないと考えられます。ただし、AIがハルシネーションを起こしたり、出願人が本来活用したい分野と全く異なる分野を提案したりすることが時々あるため、少なくとも出願内容は特許庁に提出前に丁寧にチェックする必要があります。
商標出願を徹底的に自動化
近年、商標出願手続きを徹底的に自動化するシステムが登場しています。利用者は専用フォームに商標名や事業内容、出願人情報など必要事項を入力するだけで、対面相談を行うことなく出願手続きを完了できます。これらのシステムは、特許事務所がAIを活用して、商標出願に必要な各種プロセスを最大限自動化したもので、最終的には弁理士が内容をチェックし、特許庁に提出するという流れが一般的です。一見すると、利用者の負担が軽減され、非常に効率的に思えますが、自動化が進んだ分だけ注意すべき点も増えています。商標出願は単なる書類提出ではなく、事業戦略に直結する重要な行為であるため、表面的な手続きが整っていても、出願内容が事業に適合していなければ意味がありません。また、自動化によって標準化された提案は、個別具体的な事情に対応しきれないことも多いのが現実です。本稿では、このような商標出願自動化システムの具体的な仕組みや、それに伴うリスクやデメリットについて、各観点から詳しく解説していきます。
事業内容から登録する商標の範囲を生成AIが選別
商標出願において最も手間がかかる作業の一つが、出願する商品・サービスの範囲をどこまでカバーするかを選定することです。商標権は「指定商品・指定役務」に対して発生するため、適切な範囲を設定しなければ、後から必要な権利が取れていなかったことに気づくリスクがあります。こうした選定作業を支援するために、生成AIを活用して事業内容から必要な商品・サービスを自動的に抽出・提案してくれるシステムがあります。例えば、自社の定款や事業計画書をシステムにアップロードすると、AIがその内容を解析し、商標出願に必要な商品・サービスをリストアップしてくれます。さらに、優先度の高いものを順位付けして提案する機能もあり、一見すると非常に便利に思えるでしょう。
先行商標のスクレイピング
商標出願においてもう一つ重要な作業が、先行商標調査です。すでに他者が類似の商標を登録している場合、そのまま出願しても登録が認められない可能性が高くなるため、出願前に必ず先行商標を調査し、自社の商標が登録できるかを検討する必要があります。この作業は通常、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使って手作業で調査し、該当する商標をピックアップしてリスト化するというプロセスを踏みます。しかし、最近ではスクレイピング技術を活用し、こうした調査作業を自動化するシステムも登場しています。入力した商標名に対して、J-PlatPat等から類似商標データを自動的に収集し、リスト化してくれるため、作業時間は大幅に短縮されます。さらには、スクレイピング用のプログラムそのものを生成AIに作成させることも可能となり、業務効率化が飛躍的に進むことが期待されています。
ハルシネーションの危険
生成AIを活用することで、商標出願にかかる作業時間や人手を大幅に削減することができますが、その一方でAI特有の「ハルシネーション」と呼ばれるリスクには十分注意しなければなりません。ハルシネーションとは、AIがあたかも正しいかのように誤情報を生成する現象を指し、商標出願の分野でも例外ではありません。たとえば、AIが提案する商品・サービスが、実際には特許庁の公式な典型リストに存在しない名称であったり、法律上登録が認められていない項目を含んでいるケースが考えられます。
生成AIは膨大なデータに基づいて「それらしい」回答を作り出す仕組みのため、データにない事例を聞かれた際に、もっともらしく間違った情報を提示することがあります。たとえば、AIが「これは商標登録できる項目だ」として提案してきた商品・サービスが、実は現行の商標法上では対象外であったり、そもそもビジネス慣習的に使用されない言葉だったりすることがあります。このような場合、出願人がAIの提案を信じてそのまま出願してしまうと、特許庁の審査で拒絶されるリスクが高まります。
また、出願内容そのものに誤りがあった場合、単なる拒絶で済めばまだよいですが、後に権利範囲が思わぬ形で制限され、事業活動に重大な支障をきたす恐れもあります。ハルシネーションによる誤提案は、AIが進化すればするほど巧妙になり、見抜くのが難しくなるため、最終的には人間の目で一つひとつ確認しなければならないのです。AIによる効率化の恩恵を享受しつつも、情報の信憑性や法的適合性については従来以上に慎重な姿勢が求められるでしょう。
やりたい事業活動との齟齬
生成AIは過去の膨大なデータを基に学習し、一般的な傾向に沿った提案を行うことが得意です。しかし、出願人が考えている具体的な事業活動が、業界内でも前例の少ない新規ビジネスモデルであった場合、AIが提示する商品・サービスリストが実際の事業内容と齟齬を生じるケースがあります。特に、ニッチ市場や新興分野をターゲットにする場合、既存の典型リストには該当する項目が存在しないことも多く、AIに任せたままでは出願人の意図を十分に反映することができません。
また、AIが過剰に広範な範囲の商品・サービスを提案し、必要のない区分まで出願してしまうことも考えられます。商標出願は指定する区分数に応じて費用が増えるため、無駄な区分を出願することは費用面でも大きなデメリットとなります。一方で、出願人が重要視している商品・サービスがAIの提案から抜け落ちてしまうと、本来保護すべき権利範囲を取りこぼすことにもつながります。
したがって、出願範囲の最終決定は、出願人自身が事業計画をしっかりと把握し、弁理士と相談しながら慎重に行う必要があるのです。AIの提案はあくまで「たたき台」に過ぎず、それをどのように修正し、事業内容に最適化していくかは人間の判断に委ねられる部分であることを理解しておくべきです。
人によるチェックが不可欠
AIによる自動化システムがどれだけ進化しても、最終的には人間によるチェックが不可欠です。特に商標出願においては、書類の形式が整っているだけでは不十分であり、出願内容が実際の事業計画と合致しているか、先行商標との類否判断が適切であるか、法律上の問題がないかといった観点でのチェックが求められます。AIの提案に任せきりにしてしまうと、形式的には問題がなさそうに見えても、実務上や法律上の観点で致命的なミスが含まれていることがあります。
特許庁に提出する前には、必ず弁理士が内容を精査し、必要に応じて修正・補正を行う工程が欠かせません。実際にこのチェック工程を丁寧に行うと、もはや自動化システムで時間を短縮するメリットは薄れ、従来通り人が一から対応するのと大差なくなるケースも多いのです。また、商標出願は取得した権利をどのように活用するかという観点が重要であり、そのためには事業全体の戦略や今後の展望まで踏まえた提案が不可欠です。こうした総合的な視点は、現時点ではAIには難しく、やはり人間による最終確認と判断が必要となります。
商標出願をスムーズに進めるためには、AIによる効率化と、人による綿密なチェック体制の両立が不可欠です。自動化システムの力を借りつつも、最終的には人間が責任を持って内容を確認し、事業に最適な形での出願を行うことが求められます。
人が直接対応した方が早い
当センターでは、商標出願は単なる手続き完了がゴールではなく、出願人の事業活動が円滑に進み、ビジネスを成功させるための出願支援が本質だと考えています。そのため、出願段階で出願人がどのような事業を行おうとしているのかを丁寧にヒアリングし、それに基づいて必要な商品・サービスを一緒に検討するアプローチを大切にしています。
このプロセスを経ることで、出願人の意図を正確に反映した出願書類を作成することができ、後々のビジネス展開でも権利関係で困ることがなくなります。AIシステムによる効率化は確かに便利ですが、事業内容をしっかり聴取し、それを基に適切な出願範囲を抽出する作業においては、人が直接対応した方が圧倒的に早く、かつ精度も高いのです。特にニッチな業界や新規ビジネスに関する出願の場合、AIが対応しきれない微妙なニュアンスを汲み取るには、やはり人間の判断力が必要不可欠です。
さらに、当センターでは単に「登録されればいい」という視点ではなく、将来的なビジネス展開を見据えた提案を行うことを重視しています。そのため、AI任せの自動化システムでは対応しきれない部分までサポートし、出願人が安心して事業活動を進められるような支援体制を整えています。効率化だけを追い求めるのではなく、質と成果を重視した出願支援こそが、私たちが提供すべき価値だと考えています。
まとめ
商標出願の自動化システムは、効率化やコスト削減という観点から非常に魅力的なサービスに見えます。しかし、生成AIのハルシネーションリスクや、出願人の事業内容との齟齬、人による最終チェックの必要性といった課題が存在し、すべてを任せきりにするのは危険です。特に、事業化の成功を見据えた出願を行う場合には、弁理士との対話を通じて適切な範囲を決定することが不可欠であり、AIシステムが万能ではないことを理解しておく必要があります。
AIはあくまで効率化を助けるツールであり、最終的な判断や確認は人間が責任を持って行うべき工程です。出願の手間を減らすことは重要ですが、それ以上に「事業に役立つ権利」を取得するための品質管理が欠かせません。当センターでは、効率化と正確性のバランスを重視し、弁理士による直接対応を通じて、出願人にとって最適な商標出願を実現することを目指しています。商標出願をお考えの際は是非、お気軽にご相談ください。