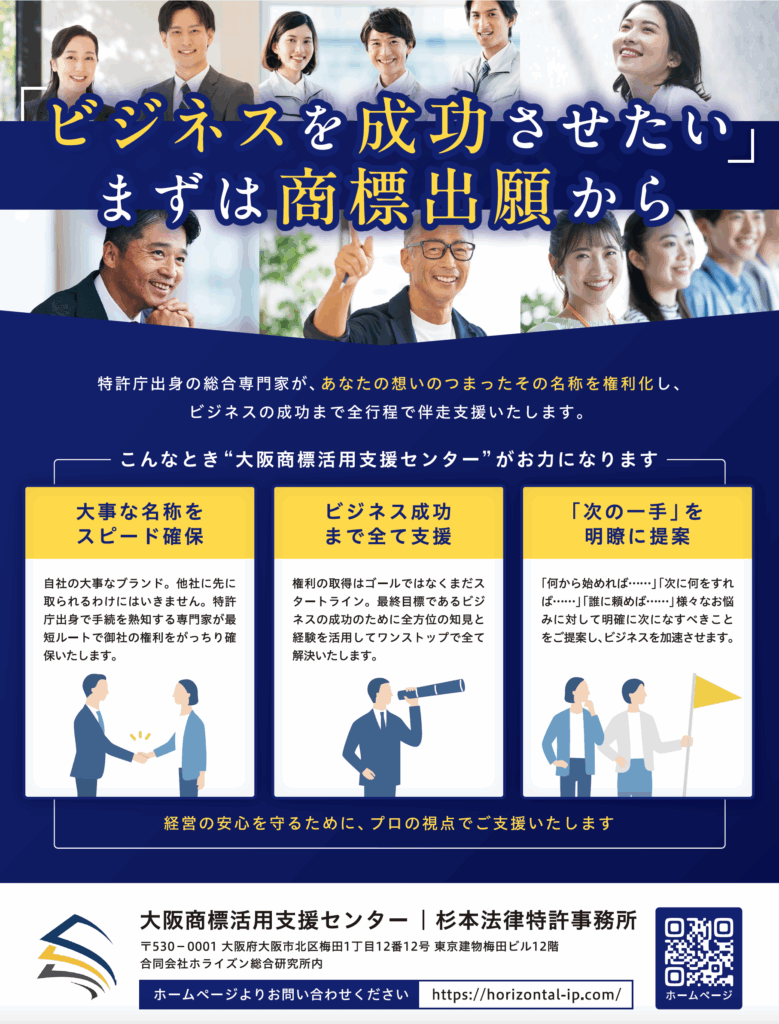相談者(40代男性)
相談者(40代男性)
上場企業の知財部に勤めています。当社では、ライバル業者が当社の特許権を無断で使用していると判断して特許訴訟の提起を顧問弁護士に依頼しようと考えているのですが、特許訴訟の提起はリスクもあるから慎重に判断した方が良いとも言われます。当社としては自社の権利を行使するだけの当然の対応だと思うのですが、どのようなリスクがあるのでしょうか。
 回答者:弁理士
回答者:弁理士
まず、特許権の侵害を相手方の取引先などには告げない方がよいです。営業誹謗だと逆に訴えられる危険があります。また、特許訴訟では多くの場合、特許権自体を無効とする反論が出てくるため、かえって藪蛇になるリスクもあります。このほか、自身では当然の権利行使だと思っていても第三者には「弱い者いじめ」に見えてしまうと企業の評価を損なってしまうなど、色々と思うようにいかない点もありますので、慎重に判断する必要があります。
特許訴訟の提起はリスクを伴う
特許権を持つ企業にとって、自社の技術を模倣されたと感じたときに最も強い手段となるのが特許訴訟の提起です。自社が長年の研究開発を経て築いた成果を守るため、法的手段を取ることは自然な発想ですし、社会的にも正当な行為と捉えられやすいものです。一般的に、訴訟というものは、侵害や損害を受けた側がそれを是正するために起こす行為であり、「被害者の正当な主張」と見なされることが多いでしょう。そのため、訴訟の提起自体に大きなリスクが伴うと考える人はあまりいません。
しかし、特許訴訟の世界では、その判断はそれほど単純ではありません。特許は、権利内容が技術的に複雑であり、かつ社会的・経済的影響の大きい知的財産権です。訴訟を起こすという行為は、単に相手を法的に責めるだけではなく、企業同士の競争関係や取引関係、さらには業界全体のバランスにも波紋を広げる可能性を秘めています。つまり、特許訴訟を提起することは、単なる法的措置というよりも、経営上の重大な決断として位置づけられます。
特許訴訟に踏み切るとき、原告となる側は「自社の権利を守る」という確信を持って臨むことが多いでしょう。しかし、相手方にとっては、その行為は単なる防衛の対象ではなく、企業の存続や信用に関わる重大な攻撃に映ることがあります。特許訴訟は、しばしば双方が徹底的に主張を戦わせる構図を生み出します。これにより、訴訟が長期化し、当初の想定を超える影響が発生することも少なくありません。訴訟の過程で、法廷外のやり取りやメディアの報道などが加わると、純粋な技術紛争にとどまらず、社会的・感情的な対立へと発展することすらあります。
特許訴訟を検討する際には、「本当に訴訟を起こすことが最善か」「別の手段で解決できないか」「企業としてどのような影響を受けうるか」といった視点を多面的に検討する必要があります。権利の保護は重要ですが、その行使の仕方を誤ると、自らの立場を損なう結果にもつながりかねません。特許訴訟の提起は、法律上の正当性だけでなく、社会的な受け止めや企業経営への影響を総合的に考慮したうえで行うべき極めて重い判断となります。
そこで本稿では、特許訴訟を起こす際に想定しておくべき具体的なリスクについて、いくつかの観点から詳しく説明していきます。
特許権侵害を第三者に告げると営業誹謗となるリスク
特許権を持つ企業が、自社の特許を侵害していると見られる商品を市場で見つけた場合、まず思い浮かぶのは「その販売をやめさせたい」という行動です。特許権者として当然の思いですが、問題はその伝え方にあります。相手方が販売している商品を取り扱う販売店や取引先に対して、「その商品は特許侵害だから扱うべきではない」と伝えてしまうと、思わぬリスクを招くおそれがあります。
このような行為は、場合によっては「営業誹謗」として訴えられる可能性があります。営業誹謗とは、他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告げたり、誤解を与える表現を用いたりすることで、取引を妨害する行為を指します。仮に「特許侵害」という発言が真実であっても、訴訟でそれを立証できなければ、虚偽の告知をしたと判断されるおそれがあります。
実際、特許侵害の有無を判断するのは容易ではありません。特許請求の範囲と製品の構造や機能を詳細に比較する必要があり、技術的な専門知識に加えて法的な解釈も伴います。特許庁や裁判所で長期間にわたって審理されるほどの複雑な問題を、権利者が一方的に「侵害している」と断定するのは非常にリスキーなのです。そのため、たとえ自社の特許を守るためであっても、第三者に対して相手の商品を「特許侵害だ」と告げることは、原則として避けるべきといえます。
権利者として主張すべき相手は、あくまで侵害者本人です。販売先や顧客など、相手の取引関係者に直接働きかける行為は、訴訟に発展した際に不利に働くことが多いです。感情的になって不用意な発言をしてしまうと、逆に損害賠償請求を受ける可能性すらあります。したがって、特許侵害を疑う場合には、まず専門家を通じて法的リスクを確認し、必要に応じて警告書の文言を慎重に検討した上で対応することが求められます。
無効化のリスク
特許訴訟を提起すると、被告側が最も強力な反撃手段として用いるのが「特許の無効主張」です。すなわち、「その特許自体が有効ではない」という主張を行い、訴訟の根本を揺るがせるのです。仮にこの主張が認められれば、特許権者がいくら侵害を訴えても、そもそも無効な特許に基づく請求は成り立たず、訴えは棄却されます。ここに、特許訴訟特有の大きなリスクが存在します。
本来、特許庁で登録された特許は、専門の審査官による厳格な審査を経ているため、簡単には無効にはならないように思われがちです。しかし、実際の訴訟の場では、特許審査時に考慮されなかった新たな先行技術文献や技術的証拠が提示されることがあります。その結果、特許が進歩性や新規性を欠くと判断され、無効とされるケースが少なくありません。つまり、「訴訟を起こさなければ維持できていた特許」が、訴訟をきっかけに失われてしまう可能性があります。
このようなリスクを軽減するために、特許権者は訴訟提起の前に、自らの特許の脆弱な部分を分析し、必要に応じて「訂正審判」を行うことがあります。訂正審判とは、特許請求の範囲を限定するなどして、無効理由を解消するための手続きです。もちろん、権利範囲を狭めることになるため戦略的な判断が必要ですが、後の訴訟で無効を突かれるリスクを抑える上では有効な手段です。
訴訟は、単に「侵害している・していない」を争うだけではなく、「特許が本当に有効なのか」という根本的な議論にまで及びます。そのため、特許訴訟を起こす前には、自社の特許の有効性を第三者目線で再確認し、少なくとも「無効を主張されても耐えられる程度の強度」があるかを検討することが重要です。
企業の信用
特許訴訟の提起は、企業の社会的評価に少なからず影響を与えます。特に上場企業や知名度の高い企業の場合、訴訟提起のニュースが報道されることで、取引先や投資家、消費者の印象に影響が及ぶことがあります。正当な権利行使である場合には「技術を大切にする企業」としてポジティブに受け取られることもありますが、訴訟相手が中小企業やスタートアップである場合には、「弱者を追い詰めている」と見られることもあります。
実際、特許訴訟提起が株価にどのような影響を与えるかを分析した調査によると、結果は必ずしも一方向ではありません。技術的優位性を示す手段として評価されるケースもあれば、対立構造の深まりや訴訟費用の増大が懸念されて株価が下落するケースもあります。つまり、訴訟提起の経済的影響は「勝つか負けるか」だけでなく、「社会がどう見るか」によっても大きく左右されます。
企業のブランド価値は、単なる製品や技術の評価にとどまらず、社会的姿勢や倫理観にも支えられています。たとえ権利の正当性があっても、過剰な訴訟戦略は「訴訟依存体質」「競合排除型の企業」といった印象を与えることがあります。特許訴訟を起こす際には、勝訴の可能性だけでなく、社会的信用や顧客イメージへの影響も慎重に検討することが欠かせません。
時間とコストを考慮せよ
特許訴訟は、一般的な民事訴訟の中でも特に時間と費用がかかる分野です。訴訟の主要な争点は、「侵害の有無」と「特許の有効性」という二つの大きな論点に分かれます。これらは技術的かつ法律的に複雑で、審理が長期化する傾向があります。第一審だけでも数年を要することが珍しくなく、控訴審・上告審まで進むと、最終判断が下されるまでに5年以上かかることもあります。
また、訴額が大きくなりやすいため、弁護士費用・鑑定費用・専門家意見書作成費などのコストも膨らみます。特許侵害訴訟の弁護士報酬は数百万円単位に及ぶことが多く、さらに訴訟の過程で社内の技術担当者や法務担当者が多大な時間を割かれることになります。つまり、直接的な費用だけでなく、人的リソースの負担という間接コストも相当大きいです。
したがって、特許訴訟を提起する前には、勝訴した場合に得られる経済的利益と、訴訟に要する時間・コストを比較し、費用対効果を冷静に見極める必要があります。損害賠償やライセンス収入が予想以上に小さい場合、訴訟費用を回収できない可能性もあります。さらに、長期間にわたる訴訟の中で市場環境が変化し、そもそも対象製品が陳腐化するという事態も起こり得ます。企業にとって特許訴訟は「正義のための戦い」であると同時に、「経営資源の配分判断」でもあるのです。
まとめ
特許訴訟の提起は、権利行使の最終手段であり、企業の知的財産戦略における重要な一歩です。しかし、その裏には多くのリスクが潜んでいます。営業誹謗の危険、特許の無効化、企業イメージへの影響、そして時間とコストの負担など、いずれも無視できない要素です。訴訟を通じて得られる成果がこれらのリスクを上回るかを慎重に判断することが求められます。
特許権は、企業の技術力を象徴する資産であると同時に、正しく使わなければ自社に跳ね返る諸刃の剣でもあります。訴訟を起こすかどうかの判断においては、感情や短期的利益に流されず、法的リスク・経済的合理性・社会的影響を総合的に検討する姿勢が不可欠です。特許訴訟は「勝つか負けるか」だけの問題ではなく、「どのように企業が信頼を築き、技術を守るか」を問う経営課題です。
当センターでは特許庁勤務経験もある弁護士・弁理士が御社の特許訴訟を慎重にリードいたします。下記よりお気軽にご相談ください。