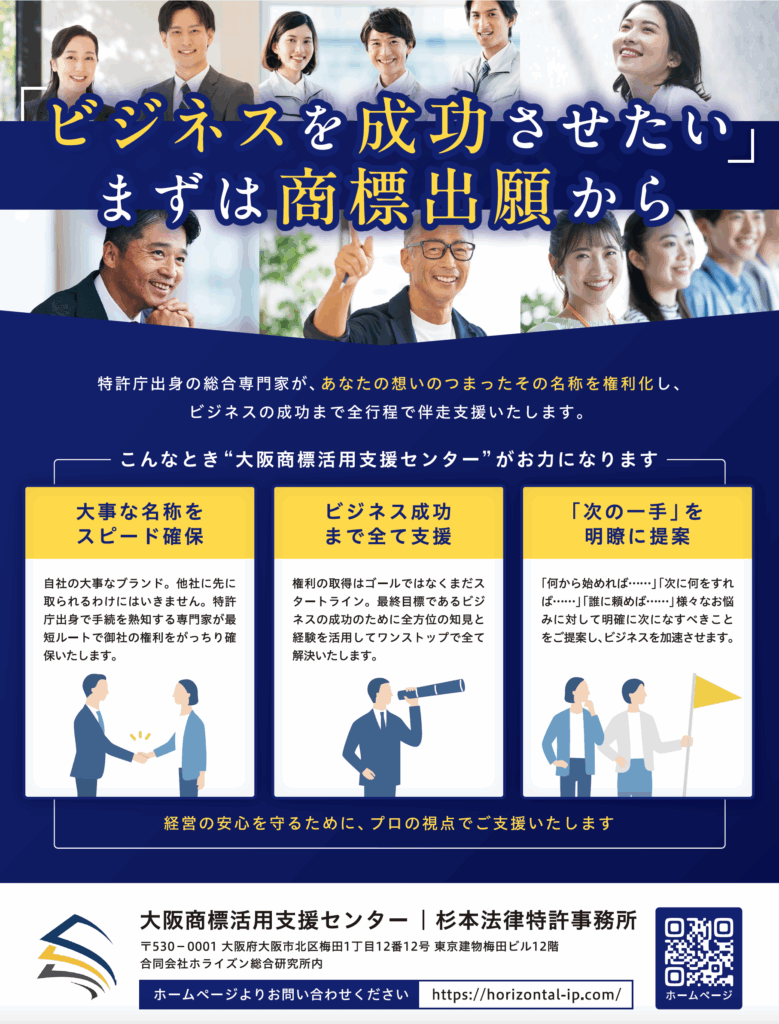商標権にも価値がある
企業経営において「商標」という言葉を耳にする機会は多いですが、その価値を具体的に数字で把握している人は意外と少ないものです。商標権は単なる名前やロゴの独占的使用権にとどまらず、法律で保護された立派な財産権の一つです。特許や著作権と同じく、譲渡したりライセンス契約を結んだりすることで取引の対象となり、金銭的な対価と交換することができます。つまり、商標権は企業の貸借対照表に計上され得る「財産的価値」を持つ権利です。
しかし、商標権は有形の資産とは異なり、手で触れたり目に見えたりするものではありません。そのため、「どれくらいの価値があるのか」という点を直感的に把握するのは難しいのが実情です。たとえば、同じ「ブランド名」であっても、消費者に広く浸透しているものと、ほとんど知られていないものでは価値が大きく異なります。また、業界や使用範囲、ライセンスの可能性などによっても、評価額が大きく変わってしまいます。つまり商標権の価値は固定的なものではなく、状況によって流動的に変わります。
このように不明確な側面を持つ商標権ですが、企業にとっては軽視できない存在です。特に現代では、商品やサービスが「機能の差」だけでなく「ブランドイメージ」によって選ばれる傾向が強まっています。そのため、商標権をどう評価し、どう財務戦略に活かしていくかは、経営判断に大きな影響を及ぼします。そこで本稿では、商標権の価値をどのように評価するのか、その具体的なアプローチや、財務戦略上の活用のポイントを整理してご紹介します。
3つのアプローチ
商標権の価値評価には、一般的に「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」という三つの方法があります。それぞれの特徴を理解することで、商標権の評価に対する考え方が整理しやすくなります。
まず「コストアプローチ」です。これは、商標権を取得するために実際に要した費用や、同じ商標を新たに作り上げるために必要とされる費用を基準にして、その権利の価値を算定する方法です。商標の登録費用、弁理士への報酬、ロゴデザイン費用などがこれにあたります。実務上は最もシンプルな考え方であり、権利発生時の評価にはよく用いられます。
次に「マーケットアプローチ」です。これは、過去に取引された類似の商標権やブランドの事例を参考にして、現在の商標権の価値を算定する方法です。たとえば、同じ業界で知名度が近いブランドの売買価格が分かれば、それを基準にして評価できるのです。株式の取引と同じく、需要と供給のバランスによって市場価格が形成されるという発想です。ただし、商標権の売買事例は限られており、参考となる市場データを入手することが難しいという制約があります。
最後に「インカムアプローチ」です。これは、商標権が将来生み出すと予想される収益を現在価値に割り引いて評価する方法です。ライセンス料やロイヤリティ収入を見込める場合、その金額を基準に計算します。将来のキャッシュフローを基礎とするため、最も理論的な評価方法といえますが、収益予測や割引率の設定によって結果が大きく左右される点に注意が必要です。
このように、それぞれのアプローチには一長一短があり、どの方法が適切かは商標権の状況や評価目的によって異なります。
権利発生当初はコストアプローチで算定
商標権が新たに発生した当初は、ほとんどのケースでコストアプローチが採用されます。なぜなら、その段階では商標がどのように活用されるか、どれほどの収益を生み出すのかといった具体的な見通しがまだ立っていないことが多いからです。したがって、取得にかかった費用をそのまま価値として計上するのが最も妥当とされるのです。
具体的には、商標登録のための特許庁への手数料、弁理士に支払った費用、ロゴやネーミングを開発するための制作費などが評価対象となります。これらの費用の合計額が、商標権の価値として貸借対照表に反映されるのです。しかし、商標の場合、登録費用そのものはそれほど高額ではなく、数万円から数十万円程度にとどまることが一般的です。そのため、会計処理上は減価償却によって早期に帳簿価額が小さくなり、最終的に「1円」として計上されるケースも少なくありません。
つまり、権利としての重要性が小さいわけではなく、あくまで会計上のルールによって簡素化された結果にすぎません。実際には、その後の事業展開によって商標権の持つ影響力は大きく変わっていきます。それでも発生当初においては、将来の不確実性が高いため、コストアプローチによる算定が現実的であると考えられています。
このように、権利の初期段階においては「取得コスト」を基準に算定されることが多いことを理解しておくことは、商標権の扱いを考える上で重要です。
権利の成長に伴い理屈上は価値が変遷するはずだが
商標権は事業が拡大し、ブランドが市場で認知されるにつれて、理論的にはその価値が高まるはずです。たとえば、知名度の高いブランド名は、それだけで消費者の購買意欲を刺激し、競合との差別化を実現します。こうした段階では、先に説明した「マーケットアプローチ」や「インカムアプローチ」での評価が理屈としては妥当になります。
しかし、実際には商標権の売買市場は活発ではなく、参考にできる取引事例が乏しいため、マーケットアプローチを実務で使うことは困難です。加えて、日本の会計基準や税法では、自社で保有している商標権の利用状況が変化しても、それを理由に評価額を見直すことは認められていません。そのため、実際には高額のライセンス収入をもたらす商標権であっても、帳簿上は依然として「1円」のまま計上され続けるという事例が珍しくありません。
インカムアプローチについても、ライセンス契約やロイヤリティ収入が現実に発生していれば理論的には有効です。しかし、会計上はあくまで「発生した収益」として処理されるだけであり、その結果として商標権自体の帳簿価額が引き上げられることはありません。つまり、事業の発展に伴って権利の経済的価値が高まっても、会計処理上はその変化を反映できないというギャップが存在します。
この点は、商標権の特殊性を理解するうえで非常に重要です。理屈上は価値が大きく変動しているはずなのに、帳簿上では静止したまま、という現象が起こり得るのです。
M&Aにより財産的価値が化ける
こうした商標権の潜在的価値が、会計上もはっきりと姿を現すのがM&Aの場面です。企業を買収する際には、その企業が持つ資産や負債をすべて「時価」で評価し直す必要があります。つまり、それまで簿価1円でしかなかった商標権が、買収交渉の過程で数億円、数十億円といった評価額に跳ね上がることがあります。
近年、特に大企業において無形資産の割合が有形資産よりもどんどん大きくなっています。その理由の1つとして無形資産がこうしてM&Aを通じて価値を高めていることが挙げられます。特にブランド力を支える商標権は、収益基盤として極めて重要であり、その価値が大幅に増加することが珍しくありません。実際に、工場や設備といった有形資産は時間の経過とともに劣化し、価値が減少していきますが、商標権をはじめとする無形資産はブランド認知の拡大によって逆に価値が増大する可能性があります。この点が、現代の企業経営における無形資産の重要性を象徴しています。
M&Aの現場では、こうした無形資産の価値をいかに見極めるかが取引価格を左右します。商標権が強力なブランド力を持っている場合、企業全体の評価額の中で大きな比率を占めることもあります。つまり、日常的な会計処理ではほとんど顧みられなかった権利が、企業の戦略的取引の場面では一気に脚光を浴びます。
したがって、商標権を単なる法的権利として扱うのではなく、将来的に大きな財務的価値を生み出し得る資産として捉え、育成していくことが、企業経営における重要な戦略と言えるでしょう。
まとめ
商標権は目に見えない無形資産であるため、日常の会計処理や財務諸表においては、その価値が十分に反映されないことが多いです。発生当初はコストアプローチによって取得費用を基準に算定され、帳簿上は小さな金額しか計上されません。しかし、事業の発展やブランドの浸透に伴って、経済的な実力としての価値は大きく変動していきます。理論的にはマーケットアプローチやインカムアプローチが妥当となる場面もありますが、会計基準や税法上、その変化を反映することはできません。
このような制約の中で、商標権の真価が現れるのはM&Aの局面です。企業全体を時価で評価し直す際に、商標権が潜在的に持っていた価値が表面化し、莫大な金額で評価されることがあるのです。現代においては、有形資産よりも無形資産が企業価値を支える割合が増加しています。その背景には、ブランドや知的財産といった無形資産が長期的な競争力を左右するという現実があります。
したがって、商標権は単に登録して終わりの権利ではありません。企業が中長期的に成長するためには、商標を戦略的に活用し、そのブランド価値を高めていく取り組みが欠かせないのです。「その商標権いくら?」という問いに即答することは難しいかもしれません。しかし、適切な評価手法と経営戦略を組み合わせることで、その答えを導き出すことは可能です。商標権をいかに活かすかが、今後の企業の成長力を大きく左右すると言えるでしょう。
当センターでは無形資産の取得だけでなく、これを育て企業価値に昇華させていくところまで総合的な支援業務を提供しております。下記よりお気軽にご相談ください。