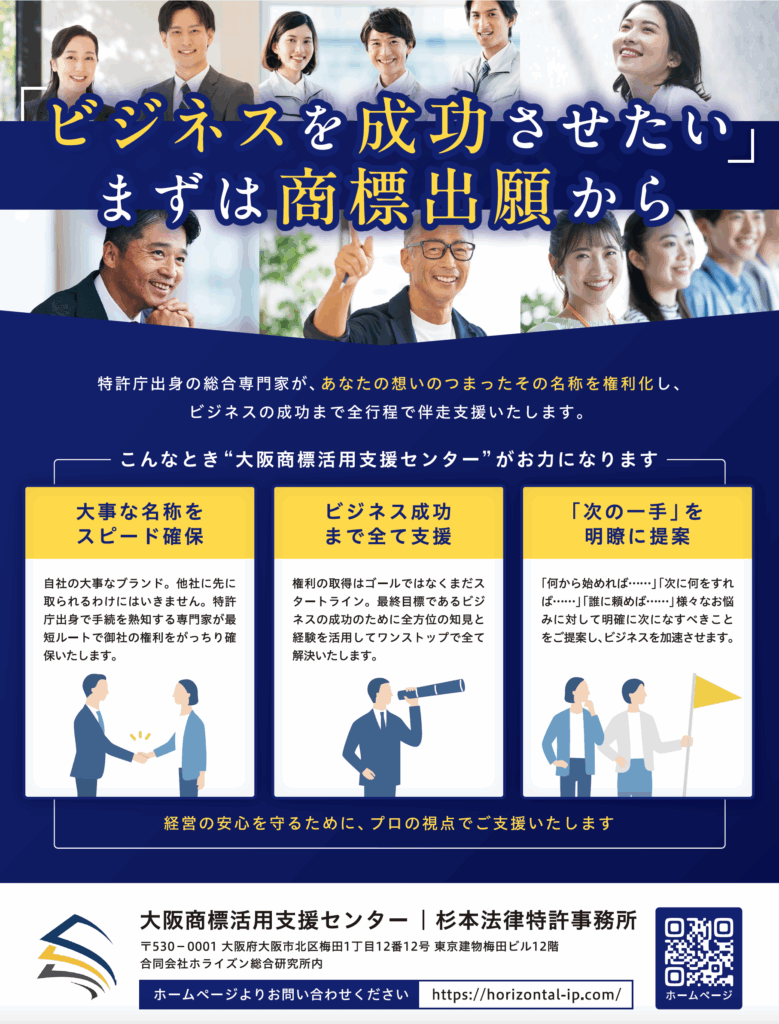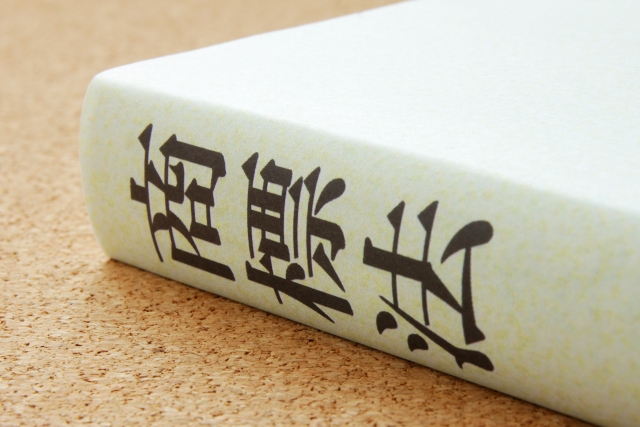
「先行類似商標があります」という拒絶理由通知は厄介
商標出願において、「先行類似商標がある」という理由で拒絶理由通知を受けることは決して珍しいことではありません。出願前には、多くの場合で先行商標調査が行われますが、現実的にはすべてのリスクを回避することは難しく、調査では拾いきれなかった登録商標に基づく拒絶理由が後から指摘されることがあります。このような拒絶理由通知は、出願人にとって非常に厄介な問題です。なぜなら、商標の類似性の判断には、称呼(呼び方)、外観(見た目)、観念(意味)の三つの要素が複雑に絡み合っており、商標全体の印象や市場での使用実態によっても判断が左右されるため、一律に回避策を講じることが難しいからです。
しかし、拒絶理由通知を受けたからといって直ちに出願を断念する必要はありません。本稿では、こうした拒絶理由通知に対して実務上よく用いられる「かわし方」について、体系的に紹介します。各手法の特徴と留意点を理解することで、出願商標の登録可能性を高め、ブランド保護を効果的に進めることができます。
先行商標と抵触しない分野に補正する
拒絶理由のうち、先行商標との類似性が指摘された場合にまず検討されるのが、指定商品または指定役務(サービス)の補正です。商標審査では、商標そのものの類似性に加えて、それが使用される商品やサービスが同一または類似しているかどうかも重要な判断要素となります。
この判断の基礎となるのが「類似群コード」という制度です。これは、商品やサービスを一定の基準でグループ分けし、審査の効率化と一貫性のために導入されたものです。同じ類似群コードに属する商品・サービスについては、たとえ商標が異なっていても、類似しているとみなされやすくなります。
したがって、指定商品・サービスを先行商標の類似群コードとは異なる範囲に補正することで、商標間に実質的な競合関係がないことを明確にし、拒絶理由を回避する可能性が生まれます。ただし、補正には期間制限があり、また出願時の範囲から逸脱するような補正は認められないため、戦略的な判断が必要です。
非類似であると争う
次に考えられるのが、先行商標との非類似性を主張する方法です。商標の類否判断は、称呼・外観・観念という三つの観点から総合的に行われます。そのため、たとえ一部の要素が似ていたとしても、全体として明確に異なる印象を与える場合には、類似していないと認められる可能性があります。
このような反論を行う際には、過去の審決例や判例を調査し、どのような事例で非類似と判断されたかを参照することが有効です。加えて、商標の使用実態や広告・宣伝の仕方、市場での認知状況などを資料として提出することにより、審査官に対して説得力のある説明を行うことが求められます。
なお、非類似の主張が成功するかどうかは、審査官の主観的判断に左右される部分もあるため、専門家による十分な分析と戦略的な反論が欠かせません。
結合商標の要部を争う
商標が複数の語句や図形から構成されている「結合商標」の場合には、その商標の全体ではなく「要部」とされる部分に焦点を当てて類否判断が行われることがあります。要部とは、その商標の中で、他と比較して自他商品識別力が強く、取引者・消費者に強い印象を与える部分を指します。
この要部の捉え方については、しばしば出願人と審査官との間で見解が分かれます。審査官が先行商標と要部が共通していると判断すれば、たとえ他の部分が異なっていても類似とされてしまう可能性があります。これに対して、出願人は商標全体の構成や使用の実態、一般的な取引慣行などを踏まえながら、要部が異なることを主張することになります。
要部をめぐる争いは、商標の印象をどう捉えるかという問題であり、極めて実務的かつ感覚的な側面を含んでいます。十分な立証資料を用意し、理論と実態の両面から説得的に主張を展開することが求められます。
不使用取消審判をする
先行商標が実際には使用されていないにもかかわらず、出願の障害となっている場合には、不使用取消審判の申し立てを検討することができます。商標法では、登録後3年以上継続して使用されていない商標について、利害関係人が取消審判を請求することが認められています。
この制度は、実際に使用されていない商標が市場で新しい商標の使用を妨げてしまうことを防止するためのものであり、特に同一又は類似の商品・サービス分野で新規参入を図る場合には重要な手段です。取消審判を申し立てるにあたっては、インターネットや企業情報、過去の広告活動などを調査し、先行商標の使用実態を裏付ける資料が存在しないことを確認する必要があります。
不使用取消審判は、制度的な手続きであり、他の反論手段に比べて客観的な基準で結果が出るため、積極的に検討すべき対策といえます。原則として霞が関の特許庁での手続となりますが、当事者双方が合意すれば地方での審判手続も行われるため、使い勝手は悪くありません。
ライセンスを受ける
先行商標の権利者と交渉し、商標の使用許諾(ライセンス)を受けるという方法もあります。これは、出願商標がどうしても自社の事業やブランド戦略に不可欠であり、他の選択肢が限られる場合にとり得る有効な手段です。
ライセンス契約により、法律上は他人の登録商標を使用できる状態が整い、実務上も商品・サービス展開を円滑に進めることが可能になります。ただし、ライセンス交渉は交渉相手の理解と協力を得る必要があるため、簡単には成立しないことも多くあります。
そのため、相手方にとってもメリットがある提案を行い、双方が納得できる形で合意を目指すことが大切です。条件や期間、地域、使用態様などについて明確に取り決めることで、後のトラブルを回避することができます。
不使用取消審判からライセンスに柔軟に移行
不使用取消審判とライセンス交渉は、排他的に選択すべきものではなく、実務上は状況に応じて柔軟に組み合わせることが重要です。まず不使用取消審判を申し立てることで、相手方に対してプレッシャーを与え、その後の交渉を有利に進める材料とするという戦略が一般的に用いられます。
先行商標の権利者にとって、商標が取消されるリスクは避けたいものであり、交渉によって一定の対価を得られるのであれば、ライセンスの提供に応じるケースもあります。実際には、取消審判の進行中に和解のかたちでライセンス契約が成立することも少なくありません。
こうした柔軟な対応は、出願商標の早期利用を可能にし、また権利関係の安定化にもつながります。複数の選択肢を視野に入れて行動することが、商標戦略の鍵となります。
まとめ
「先行類似商標があります」という拒絶理由通知は、多くの出願人にとって壁となる問題ですが、正しい知識と適切な対応をもってすれば、商標登録を実現する道は残されています。補正による範囲調整、非類似の主張、要部をめぐる争点の提示、不使用取消審判やライセンス交渉など、多様な対策を組み合わせて対応することが求められます。
特に、商標戦略は事業計画と直結する重要なテーマであり、早期の段階から専門家の助言を得ながら対応を進めることが、リスクを最小化し成功の確率を高めるために不可欠です。拒絶理由通知を単なる「壁」として受け止めるのではなく、「乗り越えるべき課題」と捉え、積極的かつ柔軟に取り組む姿勢が重要となります。
当センターでは以上のような先行類似商標対策の対応経験が豊富です。お困りの際は下記よりお気軽にご相談ください。