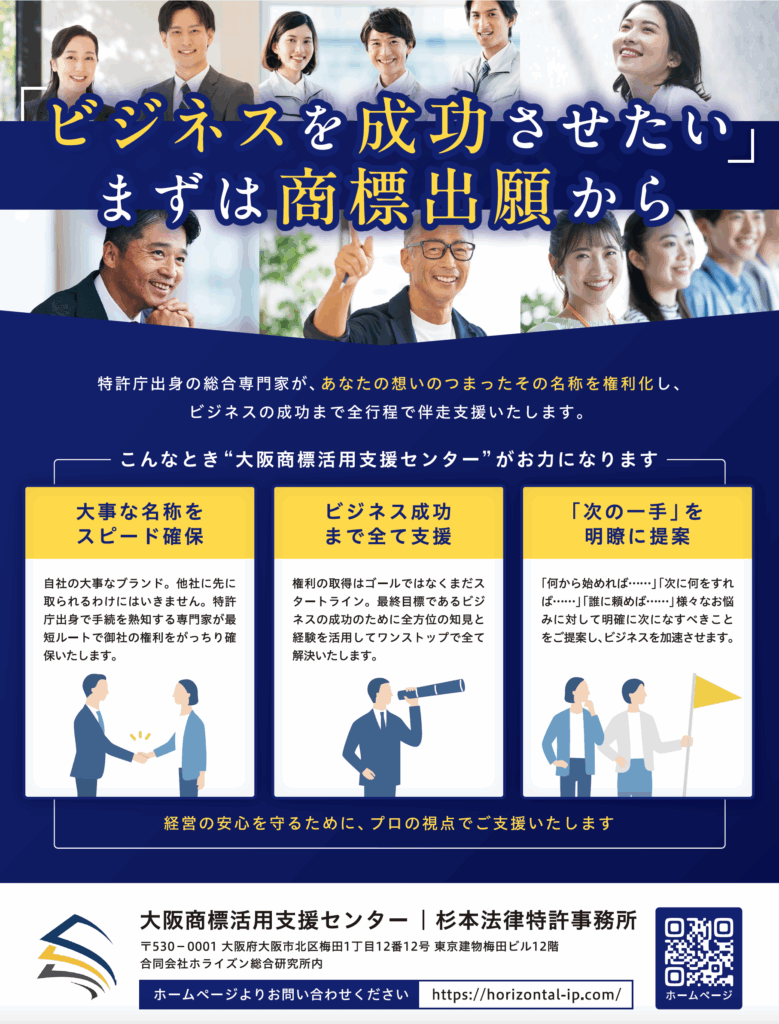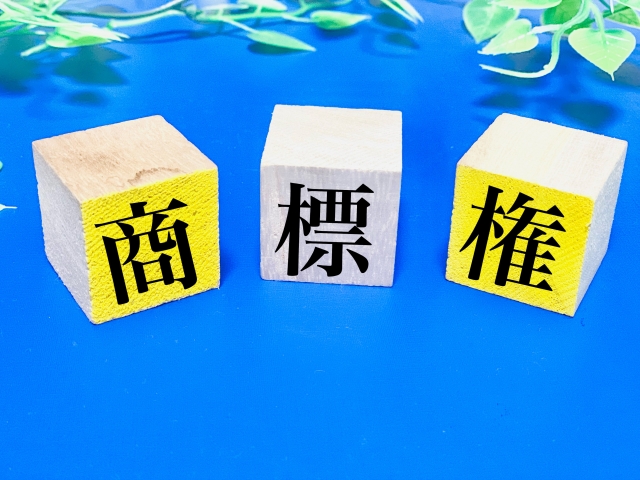
「AFURI」事件の概要
神奈川県愛川町の老舗酒蔵、吉川醸造が販売する日本酒「雨降(あふり)」と、東京を中心に展開するラーメンチェーン「AFURI(あふり)」の間で、商標権をめぐる深刻な争いが勃発しました。「雨降」は、丹沢山系の阿夫利山(あふりやま)にちなんだブランド名で、地元の自然と伝統に根ざした名称です。一方、AFURIも同じ阿夫利山をイメージソースとし、ヘルシー系ラーメンのブランド名として展開していました。問題となったのは「AFURI」が先に商標登録されていた点で、吉川醸造が「雨降」を酒類に使用することで、ラーメンチェーン側から商標権侵害として差止請求がなされたのです。名称の由来が共通し、かつ商標が類似するとの判断から、争いは訴訟と審判にまで発展し、両者にとって大きな負担を生む事態となりました。本稿ではこのケースを題材に商標出願が遅れると多大なリスクと損害が生じるおそれがあることを解説します。
吉川醸造が商標出願が遅れた理由
吉川醸造が「雨降」の商標出願を怠った背景には、いくつかの理由が推察されます。まず、「雨降(あふり)」が地元・神奈川県にある阿夫利山に由来する地名であるため、商標として独占する意識が薄かったことが挙げられます。地名や伝統的名称は誰もが使うものという感覚が根強く、「商標登録しなくても問題は起きない」と考えていた可能性が高いです。また、同様に地域資源を活用する企業やブランドに対して、「まさか攻撃的に出ることはないだろう」といった性善説的な見方があったとも推察できます。しかし実際には、ブランド間の競争が激化する現代において、先に商標を押さえた側が絶対的な優位を得る仕組みになっています。吉川醸造のように、商品開発・販売に注力していると商標戦略が後回しになりがちですが、その油断が命取りになったと考えられます。このケースでは、どうしても後発のラーメンチェーンの方を悪役に見立てる記事も多いのですが、早い者勝ちの商標の世界ではすぐに商標出願したラーメンチェーンの方が正常な対応で、吉川醸造は後手に回ったと言わざるをえません。

「雨降」と銘打った酒類すべての廃棄要求
ラーメンチェーンAFURI側から商標権侵害の指摘を受けた吉川醸造は、「雨降」というブランド名で展開していた日本酒のすべてに対して、販売中止と破棄を要求されました。特に、瓶やラベル、広告物などに「雨降」の文字を印刷していたため、すべての商品資材が使用できなくなり、販売再開の目処も立たなくなってしまいました。さらに、酒類販売においてはブランドの蓄積と信頼が命であり、単に名称を変えれば済む問題ではありません。すでに市場に出回った商品を回収することも難しく、問屋や小売業者からの信用にも悪影響が出始めていました。長年かけて育ててきた銘柄を一夜にして失うリスクに直面し、会社全体の営業活動が大きく揺らぐ事態となったのです。この危機は、単なる法的争いではなく、事業継続そのものを揺るがす深刻な局面を迎えていました。

事後的な対策が難航
吉川醸造は「雨降」に関する商標トラブルが発覚した後に弁護士に相談に言ったと推察されます。しかし、すでにAFURI側が類似商標を取得済みであった以上、事後的な対策は極めて困難な状況にありました。まず、相手が有効な商標権を持っている限り、こちらが商品名の使用を継続するには、「無効審判」や「不使用取消請求」といった手続きを通じて商標の効力を排除するしかありません。しかし、それには時間も費用もかかり、勝訴の可能性も高くはありませんでした。さらに「雨降」という名称が他人の商標と類似していないことを証明するには、消費者の混同可能性を否定する必要があり、その証明はきわめて困難です。商品は止められ、費用はかさみ、勝訴の見込みは不明。事後対応では選択肢が極めて限られ、あらゆる面で後手に回らざるを得なかったのが実情です。

相手が商標を使用していれば不使用取消請求は難しい
商標争いにおいて、相手の商標権を無力化する最も代表的な手段の一つが「不使用取消審判」です。これは、登録から3年以上経過した商標で、実際に使用されていないものについて、取消を求める手続きです。しかし、これはあくまで「不使用」であることが条件です。たとえば、AFURI側が自社のラーメン店で「AFURI」という名称を日常的に使用し、広告やメニューに掲載していたとすれば、それは「使用実績」として十分に有効です。このような証拠が存在する限り、不使用取消審判は成立しません。また、使用の証拠は比較的ハードルが低く、たとえ地方の一店舗であっても、継続的に商標を使っていれば使用と認められる場合がほとんどです。つまり、商標を使っている側に対してはこの攻撃手段は通用せず、他の法的手段を講じる必要があるというのが、商標戦における現実なのです。

類似していない、という主張は意外に難しい
「雨降」と「AFURI」は、漢字とアルファベットで表記が異なるため、一見すると全くの別物のようにも見えます。しかし、商標審査や裁判においては「称呼(読み方)」や「外観」「観念(意味)」など多面的な基準で類似性が判断されます。両者は「アフリ」という全く同じ読み方を有しており、この点で称呼が一致します。さらに、阿夫利山という共通の語源を持つことから、観念面でも共通性があります。このように、読みや意味が一致していれば、表記の違いがあっても「類似」と判断される可能性は非常に高いのです。そのため、「雨降」と「AFURI」は似ていない、という主張は現実的には難しく、特に飲食・食品と酒類といった商品カテゴリ間では、消費者の混同が起こりうると判断されるケースも少なくありません。商標の世界では、単なる文字の違いだけでは、差異を主張するには不十分なのです。
そして、このケースでは令和5年3月に入ってお互いに相手の商標を意識した新商標を出願しており、自体は一層混迷を極めることとなりました。

時にほんの数秒の差が明暗をわけることも
ラーメンチェーンの第3商標と、吉川醸造の第4商標の出願日の差はわずか8日ですが、例えわずかであっても、商標の世界では先願者が100%勝つ仕組みとなっています。
商標権は「先願主義」を原則としています。これは、早く出願した者に優先権が与えられる制度で、仮に同じ商標であっても、後から出願した者は登録が拒否されるか、他人の商標権を侵害しているとみなされます。特にオンラインでの商標出願が主流となった今、コンマ数秒で同種の出願がなされることは決して稀ではありません。今回の「AFURI」商標でも、吉川醸造が「雨降」で出願していなかったことがすべての発端であり、たった1日でも早く出願していれば、逆にラーメンチェーン側が使えなかったかもしれません。この制度は公平である一方、知的財産の保護を後回しにした企業には大きな痛手となりかねず、「時間」が商標戦争の勝敗を決定づける要素であることを如実に示しています。
訴訟・審判合戦に。弁護士費用は?
吉川醸造とAFURIの間で発生した商標権争いは、単なる警告文の送付や交渉にとどまらず、審判請求や複数の訴訟へと発展しました。商標の使用差止請求、損害賠償請求、登録取消審判などが並行して行われ、法的手続きが複雑化したことで、吉川醸造は数千万円規模の弁護士費用と時間的コストを強いられたと推察されます。とくに商標紛争においては、専門性の高い弁護士が必要であり、その分費用も割高になります。1件あたり数百万円単位の請求が生じることも珍しくなく、審判や訴訟が長引くことでコストはさらに膨れ上がりました。加えて、審理の過程で必要となる証拠資料の収集や、過去の使用実績の整理など、通常業務にも大きな支障をきたしました。結果として、この商標争いは企業体力を大きく消耗するものとなり、営業損失以上に、精神的な負担と費用の重みが経営を圧迫したのです。そして、これらの訴訟は明確な勝算を持って追行できたものではないため、吉川醸造としては「敗訴したら営業できなくなる」という事業リスクを常に抱えながらの対応となり、精神的にも大変辛い状況であったと推察されます。
最初から商標を取得しておけば発生しなかった手間と費用
今回の一件で明らかになったのは、商標出願のタイミングがいかに重要かということです。吉川醸造が「雨降」という銘柄を商品化する段階で商標出願をしていれば、後から「AFURI」との衝突を避けられた可能性が高く、訴訟や審判といった法的対立も不要だったと考えられます。実際、出願時の費用は数万円から十数万円程度であり、弁護士費用や商品の廃棄費用、営業損失と比べれば微々たるものです。また、出願によって商標が守られていれば、逆に他者から商標を奪われるリスクもなく、安心してブランド構築が進められます。多くの企業がブランド立ち上げと同時に商標出願を行うのは、まさにこうしたトラブルを未然に防ぐためです。「商標は後でいい」という油断が、結果的に何百倍もの損失を招くという事例は、これまでにも数多く報告されています。経営の観点から見ても、商標の先行取得はもはや必須のリスク管理手段なのです。
商標は早く取得するのが必須。時に、商品販売よりも前に取得するケースも
商標権は、商品やサービスのブランド価値を守る「盾」であり、競争が激化する市場においては企業存続の基盤でもあります。今回の吉川醸造とAFURIの紛争が示すように、商標を巡るトラブルは企業イメージの失墜、販路喪失、膨大な費用負担へと直結します。そのため、多くの企業は商品開発と同時進行で商標出願を進め、時には発売前に先行して取得することも一般的です。特に現代では、商標検索もオンラインで簡単に行え、出願手続も電子化されています。つまり「面倒だから後回しにする」理由はもはや存在しません。事前に商標を取得していれば、競合との衝突も防げ、安心して長期的なブランド戦略を描くことが可能となります。経営戦略として商標を「コスト」ではなく「投資」と捉えることが、今後ますます重要になっていくでしょう。商標権の取得は早ければ早いほど、企業にとってのリスクヘッジ効果が大きくなるのです。
今回の吉川醸造とAFURIの商標権争いは、地域に根ざした伝統産業と都市型ブランドとの間で起こる衝突の一例でした。商標は単なる言葉ではなく、法的権利として厳密に管理され、先に取得した者に強い力が与えられます。商標出願を後回しにした代償は、数百万円規模の費用や信頼の喪失といったかたちで跳ね返ってきます。この事件から、企業規模や業種にかかわらず、「商標を守ることの大切さ」がよくわかるかと思います。
商標出願は当事務所でお早めに
商標出願は出来る限り早くする必要があります。しかし、早ければそれで良いわけではなく、その後の事業化に必要な範囲を網羅していなければ「ただ権利を取っただけ」になってしまいます。そこで、当事務所ではスピードを最大限に意識しながらも、必要な範囲の網羅を徹底的に意識した出願活動を行っており、権利成立後の事業展開のご相談にも幅広く対応しております。また、審判・訴訟の対応件数も多く、裁判所や特許庁での手続の経験が豊富です。商標を取りたいなと思われましたらアイディア段階でも全く問題ありませんので、当事務所にお気軽にご相談ください。