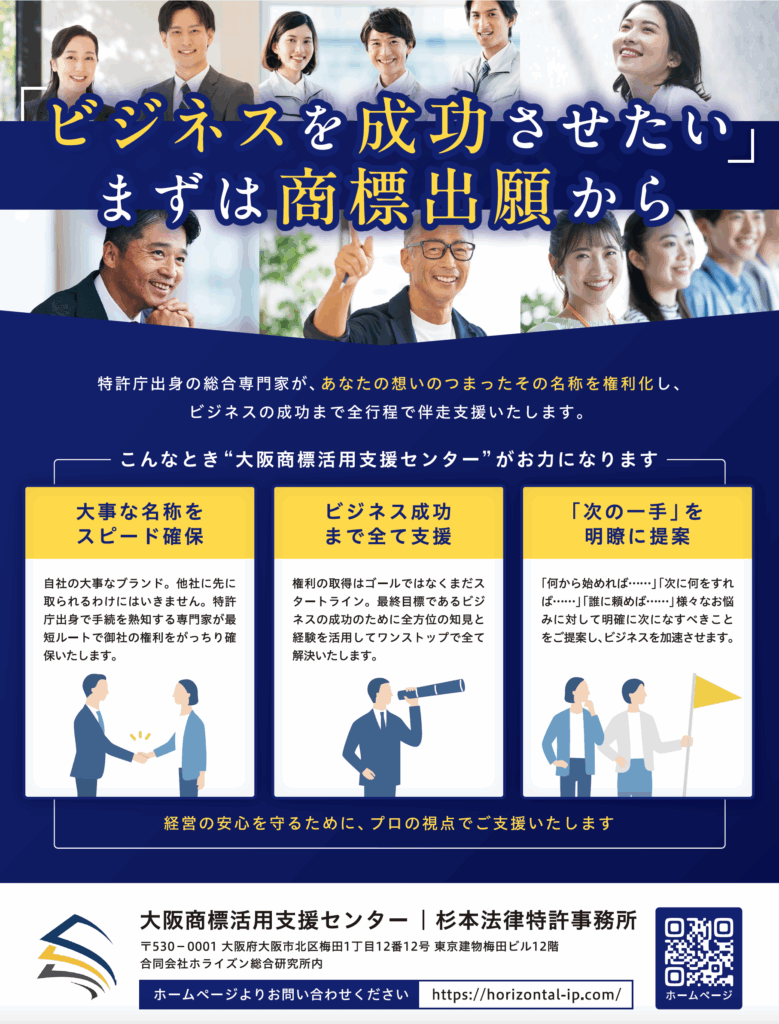日本国内の動向だけ見ていれば良い?
自社の事業展開が日本国内のみで完結している場合、通常は国内市場に関する情報を重視し、海外の動向まで視野に入れる必要はあまり感じないものです。特に商標の管理においても、「日本国内で自社の商標が不正に使われていないか」「他社に似た商標を使用されていないか」という観点に絞って活動している企業が多いのが現実です。たとえば、自社のブランド名やロゴが他者に無断で使われていれば、損害賠償請求を行ったり、差止請求を行うといった法的対応を取ることが可能です。そのため、国内の商標登録を済ませておけば、ひとまず安心だと考える経営者も少なくありません。
しかしながら、商標というのは単に「国内市場での名前の保護」ではなく、「国際的にブランドの信用を守る」ための道具でもあります。特に近年、アジア市場の経済的結びつきは一段と強くなっており、国内だけで営業している企業でも、アジア諸国の動向が思わぬ形で自社に影響を与えるケースが増えています。輸出を行わなくても、商品やサービスの情報がインターネットを通じて海外に瞬時に届く時代です。すると、他国の企業が日本企業の商標やブランド名を参考にして、先に商標出願をしてしまうといった事態が発生します。
「自分の会社は国内だけだから海外商標は関係ない」と考えていると、知らないうちに自社のブランドが海外で登録され、逆に日本での活動が制限されるリスクすらあります。そこで本稿では、なぜ日本国内のみで営業している企業であっても、少なくともアジアの商標事情には注意を払うべきなのかを、順を追って説明していきます。
5大特許庁
世界の知的財産権の保護体制は、国や地域ごとに存在する特許庁によって支えられています。その中でも特に重要なのが「5大特許庁(IP5)」と呼ばれる存在です。これは、世界で最も多くの特許・商標出願が行われている5つの特許庁を指し、具体的には日本特許庁(JPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)、欧州特許庁(EPO)、そして米国特許商標庁(USPTO)の5機関です。この5大特許庁が受け付ける出願数だけで、世界全体の知的財産出願の大半を占めています。
ここで注目すべきは、このうち3つが東アジア、つまり日本・中国・韓国に集中しているという事実です。東アジアは経済圏としての結びつきが強く、製品の模倣やブランドの流用も頻発している地域でもあります。したがって、同じ商標であっても、それぞれの国で別の企業が権利を持っているということが起こりやすいです。
特に漢字文化圏であるこの3か国では、同じ文字表記の商標が偶然または意図的に出願されるリスクが高まります。たとえば、日本で「青龍」という名前で人気の飲料を販売している企業があったとします。この場合、中国や韓国でも同じ「青龍」という商標が出願される可能性があります。そして、もし日本企業がまだ出願していない状態で現地企業が先に権利を取ってしまうと、日本企業はその国で「青龍」という名前を使えなくなる恐れがあります。
こうした状況は、もはや「海外でビジネスをしている企業」だけの問題ではありません。たとえ国内完結型のビジネスであっても、アジア市場での商標権の動きが将来的に自社に跳ね返ってくる可能性があります。
中国や韓国で先に取得されて日本に侵略されるケース
日本企業の多くは、商標出願のスピードという点で海外企業に遅れをとっています。特に中小企業の場合、商品の人気が出てからようやく商標出願を考えるというケースが珍しくありません。これは、「商標登録には費用がかかる」「まだ売れるか分からないうちは出願する意味がない」といった考え方が根底にあるからです。しかしこの「慎重さ」が、結果として海外企業に先を越される大きな原因になっています。
中国や韓国では、日本の新商品や人気ブランドが話題になると、その商標を自国でいち早く出願する動きが活発です。いわゆる「商標ハイジャック」と呼ばれる行為で、彼らは先願主義(先に出願した者に権利が与えられる制度)を利用して権利を取得します。こうして中国や韓国の企業が商標を先に取得すると、その名前を使った商品を現地で販売したり、日本向けに逆輸入したりすることが可能になります。結果として、日本企業が自国で築いたブランド価値が海外企業の手で利用され、日本市場に逆輸入されるという構図が生まれます。
たとえば、ある日本のアパレルブランドが国内で人気を集めた際、数か月後には中国企業がそのブランド名を中国商標として登録してしまった事例があります。日本企業が中国進出を考えたときには、すでにその名前が使えず、仕方なく別ブランドを立ち上げざるを得なくなりました。こうした事例は増加の一途をたどっており、特に漢字を用いた商標は意味が理解されやすいため、模倣や先行出願のターゲットになりやすい傾向があります。
つまり、「国内には競合がいない」と安心している間に、海外で自社商標が取られ、その権利を利用して逆に攻め込まれるリスクが現実に存在します。こうした背景から、日本企業であっても商標戦略においては中国や韓国の動向を無視できなくなっています。
商標は早く出願し、危険因子から守り抜く
商標権の世界では「先に出願した者が勝つ」という原則が基本です。日本にも「先使用権」という制度があり、出願よりも先に商標を使用していた場合に一定の保護を受けられることがありますが、その要件は極めて厳しく、裁判で認められることはまれです。したがって、実務的には「思いついたらすぐ出願する」ことが最も有効な防衛策になります。
また、商標権を取得した後も油断はできません。他社による不正利用や、一定期間商標を使っていない場合に行われる「不使用取消請求」など、商標には常にリスクがつきまといます。さらに、こうしたリスクは国内だけでなく海外にも存在します。特に中国や韓国では、他国の商標を監視して登録を狙う業者が存在し、これらの国で権利を奪われると、国際的な取引にも影響が出かねません。
そのため、商標を守るには「早期出願」と「継続的監視」の二本柱が欠かせません。社内で使用するすべての商標をリスト化し、それぞれの使用状況を定期的に確認する仕組みを整えることが重要です。また、国内外の商標データベースを検索し、類似出願がないかを監視することも必要です。最近ではAIを活用した商標モニタリングサービスも登場しており、こうしたツールを利用すれば、海外の動向も含めて迅速にリスクを把握できます。
危険因子を早期に察知するには、情報アンテナを広く張ることが求められます。ニュースやSNSなどで話題になった製品やブランドが、他国でどのように扱われているのかを注視することで、被害を未然に防ぐことが可能になります。商標を守り抜くという意識を、国内外問わず持つことが、これからの時代には不可欠です。
専門家を頼ろう
とはいえ、特に中小企業にとって、国内の営業活動に加えて海外の商標動向までチェックするのは容易ではありません。日々の業務で手一杯のなか、外国語で書かれた特許・商標情報を読み解くのは現実的に難しいものです。こうした場合には、専門家を活用するのが最も効果的です。弁理士や知的財産コンサルタントの中には、中国や韓国の商標制度や実務に精通した専門家が多数存在します。
専門家を通じて海外出願の必要性を判断したり、模倣リスクを分析してもらったりすることで、企業は余計な出費やトラブルを未然に防ぐことができます。また、万が一、海外で商標を先に取得されてしまった場合でも、専門家を通じて異議申立てや無効審判といった法的手段を迅速に取ることが可能です。自社だけで抱え込むよりも、外部の知恵を借りる方が、結果的にコストを抑えられるケースも多いです。
さらに、商標の専門家は単なる防御策の助言者にとどまりません。海外の商標事情を通じて、将来的な市場展開のヒントを得ることもできます。たとえば、中国や東南アジアで似た名称の商品が人気を集めている場合、それは自社商品が海外でも受け入れられる可能性を示しているとも言えます。つまり、商標リスクを監視することが、同時に海外進出のチャンスを見極める作業にもなります。
国内完結型のビジネスであっても、アジアの商標動向に目を向けることは、単なる防衛ではなく「未来への投資」と言えます。専門家のサポートを得ながら、広い視野でブランドを守り、育てていくことが、これからの中小企業には求められているのです。
まとめ
これまで見てきたように、「国内でしか営業していないから海外の商標は関係ない」という考え方は、現代のビジネス環境では非常に危険です。日本企業の商標が海外で先に登録される事例は増加しており、その多くは中国や韓国といった近隣諸国で発生しています。こうしたリスクを防ぐためには、商標をできるだけ早く出願し、定期的に監視し、必要に応じて専門家の支援を受ける体制を整えることが重要です。
アジア市場は文化的にも経済的にも日本と密接に結びついています。だからこそ、国内だけを見て安心するのではなく、広い視野でブランドの防衛線を張ることが求められます。商標管理は企業の信頼と価値を守る第一歩です。アジアの動向に目を向けることこそが、これからの企業にとって最も現実的で、そして最も賢明な選択だと言えるでしょう。
当センターでは英語もビジネスレベルで活用できる弁理士が御社の知財戦略を世界レベルの目線で高度化することに尽力いたします。下記よりお気軽にご相談ください。