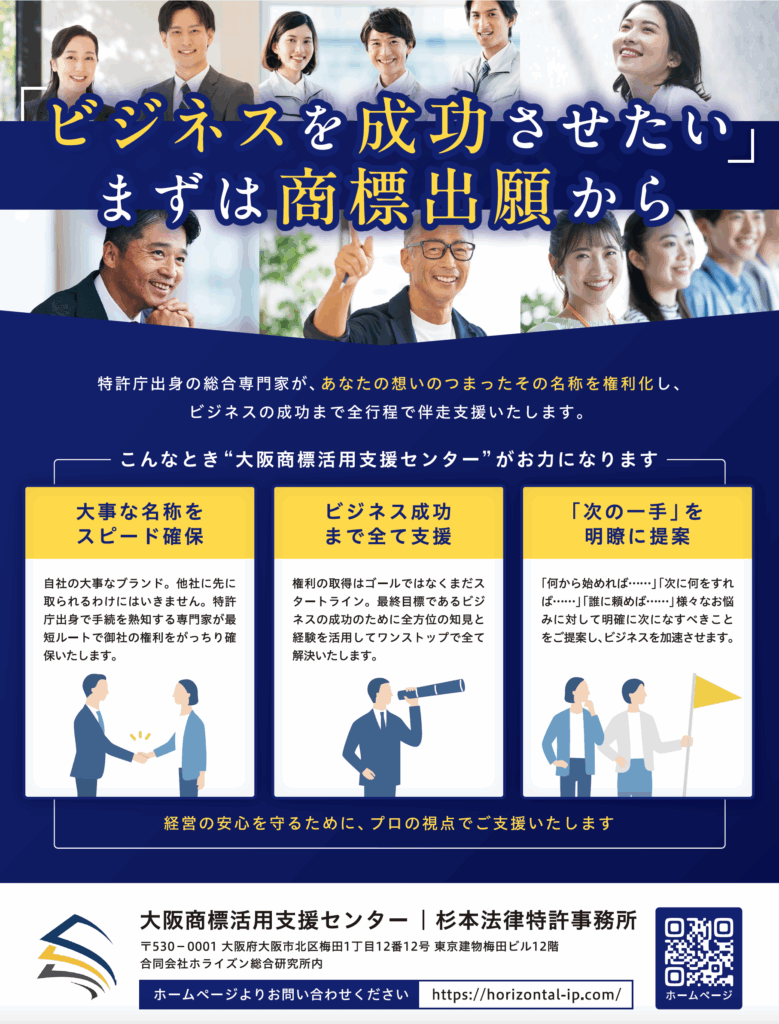生成AIの作成した画像が他者の権利侵害になるケースが頻発
近年、画像生成AIは急速に普及し、誰もが簡単に高品質なイラストや写真風の画像を作成できるようになりました。SNSや広告、商品デザインのアイデアスケッチなど、用途は多岐にわたり、クリエイティブ活動の幅を大きく広げていることは間違いありません。しかし、こうした生成AIが作成した画像は完全なオリジナルとは限らず、他人の権利を侵害してしまうリスクが頻発しています。
その理由は、AIが無から新しい画像を生み出しているわけではないからです。生成AIは大量の既存データを学習しており、その中から特徴を抽出し組み合わせて新しい画像を作成します。ところが、この過程で既存の画像の一部をそのまま再利用してしまったり、著名なデザインやキャラクターの要素が意図せず混入してしまうことがあり、これが権利侵害につながってしまいます。
また、権利侵害の有無は一般の利用者には判断が難しい点も大きな問題です。一見オリジナルに見える画像でも、元ネタとなる作品や商品と酷似している場合、権利者から指摘を受けるリスクがあります。そしてもし訴えられれば、多額の損害賠償義務を負う可能性があり、個人や小規模事業者にとっては大きな負担となります。
生成AIの普及は便利さと表裏一体でリスクを抱えています。こうした状況を踏まえ、私たちは生成AIを無防備に使うのではなく、どのようなケースで権利侵害が起こりうるのか、どのように注意すべきかを理解する必要があります。そのうえで、安全に利用するための知識を持つことが不可欠です。そこで本稿ではこうした生成AIによる権利侵害のパターンとその対策を紹介します。
バンダイが商標権侵害の警告
生成AIによる権利侵害のリスクは、すでに具体的な事例として表面化しています。その代表例として挙げられるのが、バンダイが商標権侵害の可能性について警告を発した件です。フィギュアを生成してくれるAIを用いた作品において、バンダイの商標が無断で利用されてしまうケースが報告されました。
生成AIは学習データとして大量の画像を取り込みます。その中には、バンダイが長年にわたり展開してきた人気キャラクターやロゴ、製品パーツの写真も含まれている可能性が高いです。結果として、AIが自動的に生成するフィギュアのパーツやアクセサリーに、バンダイの商標が付加されるケースが少なくありません。
特に著名な商標は、多くの関連画像に一様に表示されているため、AIはそれを「一般的なデザイン要素」と誤解して学習してしまいます。そのため利用者が意図せずとも、生成された画像やフィギュアのデザインの中に、商標やロゴが入り込んでしまいます。
商標が含まれている生成物は、一般人から見れば商標権者が公式に製作した正規品と誤認されやすくなります。これは商標法上の大きな問題であり、結果として利用者は商標権侵害に問われる可能性があります。さらに、侵害が故意でなくても免責されるわけではなく、損害賠償や差止請求を受けるリスクは消えません。
このような事例は、商標権者のブランド価値を守るための当然の警告であり、利用者側も軽視してはならない問題です。生成AIを用いる際には、出来上がった作品に商標やロゴが混入していないか、注意深く確認する姿勢が不可欠です。
注意すべきポイント
生成AIを利用する際に特に注意が必要な点はいくつか存在します。まず第一に、前章で触れたような著名な商標が自動的に盛り込まれてしまう可能性です。企業ロゴや商品パッケージに使われている特徴的なマークなどは、学習データに多数含まれているため、AIが頻繁に生成結果に取り込んでしまう傾向があります。
商標に関しては、単なる文字や図形だけでなく、特定の形状や配置を保護する「位置商標」や「立体商標」といった新しい商標制度にも注意を払う必要があります。例えば、特定の位置に付されたワンポイントデザインや、独特の形をした商品の外観も商標権として保護されている場合があります。見た目に単純な形状であっても、権利として登録されていれば侵害に該当しかねません。
さらに、商標登録がされていなくても、著名な表示を無断で使用すれば不正競争防止法違反となる可能性もあります。たとえば、有名ブランドの配色や配置が模倣された場合、一般消費者が誤認するおそれがあると判断されれば、違法とされるのです。
加えて、著作権一般にも注意が必要です。アニメキャラクターや有名イラストレーターの作風を模倣した画像は、著作権侵害とされる場合があります。また、実在する著名人の顔を模した画像では、肖像権やパブリシティ権の侵害が問題となる可能性があります。芸能人やスポーツ選手の画像を勝手に生成し、それを商業利用する行為は特に危険です。
このように、生成AIの成果物には多様な権利リスクが潜んでいます。単純に「自分で作ったものだから自由に使える」と考えるのは危険であり、事前のチェックと知識が不可欠です。
利用規約をよく読みましょう
生成AIを利用する際に最も軽視されがちなのが、サービス提供者が定める利用規約の確認です。しかし、これは利用者が権利侵害のリスクを理解し、自己責任で行動するための重要な手掛かりとなります。
多くの生成AIサービスでは、利用規約の中で「生成された画像に関する権利関係について、サービス提供者は責任を負わない」と明記しています。つまり、もし生成物に他者の権利を侵害する要素が含まれていた場合、その責任は全て利用者自身が負わなければならないのです。
このような条項は一見冷たいように思えますが、AIの仕組み上避けられない問題であるため、提供者が責任を免れるのは合理的ともいえます。むしろ、利用者は「権利侵害のリスクが高い」という前提でサービスを利用していることを意識するべきです。
また、利用規約には生成物の利用範囲についても制限が設けられていることがあります。商用利用を禁止している場合や、特定の業種での利用を制限している場合など、細かい条件が付与されていることも少なくありません。これを読み飛ばすと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
もし「利用規約を確認するのは面倒だ」と感じるのであれば、そもそも生成AIを利用するべきではありません。権利問題に関して責任を負う覚悟がない人にとっては、リスクが大きすぎるからです。したがって、安全に利用するためには、必ず利用規約を丁寧に確認し、理解した上で活用することが求められます。
慎重な判断を
生成AIの作成した画像を利用するにあたり、最も安全なケースは自己の観賞用にとどめる場合です。この場合、基本的には著作権侵害や商標権侵害といった問題は生じません。しかし、外部に公開した途端に法的問題が発生するリスクが高まる点には十分注意する必要があります。
例えば、SNSに投稿する、ウェブサイトに掲載する、商品に利用するといった行為は、すべて外部への公開にあたります。この段階で、生成物が他者の権利を侵害していた場合、権利者から削除要請や損害賠償請求を受ける可能性が出てきます。したがって、公開前には必ず画像を入念に観察し、怪しい要素がないか慎重にチェックしなければなりません。
ただし、個人の判断にはどうしても限界があります。専門知識がない利用者が権利侵害の有無を完全に見抜くことは難しいため、疑わしい場合には弁護士や知的財産に詳しい専門家に相談することが望ましいです。専門家の助言を受けることで、リスクを大幅に減らすことができます。
もっとも、いくら慎重にチェックしても「絶対に大丈夫」という保証は存在しません。生成AIは本質的に既存データを利用しているため、どこかにリスクが潜んでいる可能性は常に残ります。そのため、「100%安全」という思い込みを持たず、リスクを抱えたうえで利用しているという自覚が重要です。利用者はそのことを肝に銘じ、常に慎重な判断を下す姿勢を持たなければなりません。
まとめ
画像生成AIは私たちの創作活動を大いに助ける一方で、多くの権利リスクを内包しています。生成AIが作成した画像が完全なオリジナルである保証はなく、商標や著作権、肖像権などを侵害する可能性があります。実際にバンダイが警告を出した事例のように、商標権侵害は現実の問題として顕在化しています。
利用者が気を付けるべきポイントは多岐にわたり、商標や著作権だけでなく、不正競争防止法やパブリシティ権といった他の法的領域も含まれます。そして、多くのAIサービスの利用規約は責任を利用者に委ねているため、規約をよく読み、リスクを理解したうえで利用することが求められます。
最終的に、生成AIを安全に活用するためには「慎重な判断」が欠かせません。観賞用にとどめるならば比較的安全ですが、外部に公開する場合には必ずチェックと確認を怠ってはなりません。それでも100%の安全は保証されないことを理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
生成AIは大きな可能性を秘めていますが、安易に利用すれば深刻なトラブルを招きかねません。その利便性に浮かれるのではなく、常にリスクを意識して慎重に使うことが、私たちに求められる姿勢といえるでしょう。
当センターでは生成AIに関する法的・会計的な問題について様々な角度からその解決を試みます。下記よりお気軽にご相談ください。